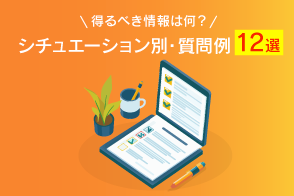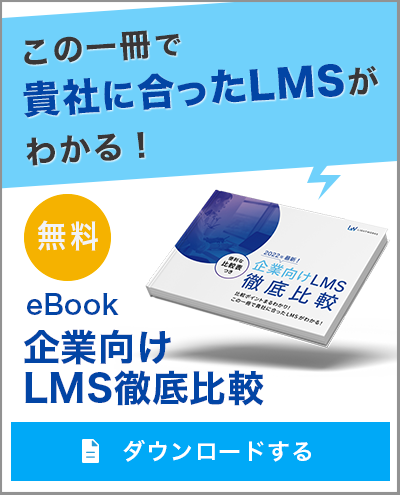研修の効果測定で成果を見える化!測定方法と指標、企業事例を解説
最終更新日:
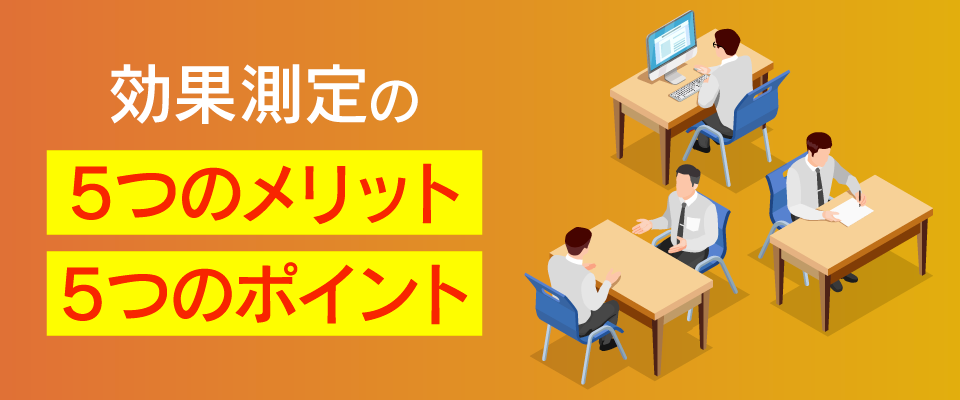
「研修の効果測定の重要性は分かっているが、忙しくて十分にできていない」
「どうすれば成果につながる効果測定ができるのだろうか」
多くの企業が人材育成のため研修の効果を追求する一方、研修の効果測定となると、その難しさや手間のかかり具合から、十分にできていないという場合も多いようです。
しかし、研修効果アップには成果の見える化と的確な改善が不可欠で、そのためには効果測定は避けては通れないのです。
さらに現在、社会状況の変化や、それに伴う研修テーマの多様化、人的資本の情報開示の義務化などにより、研修の成果を明確にすることの重要性は従来よりも格段に高まっています。
この記事では、研修の効果測定の基本から、実践的な効果測定の方法やポイント、LMS(Learning Management System:学習管理システム)を活用した効果測定の効率化、研修効果の「見える化」に成功した企業の事例まで分かりやすく解説します。
正しい効果測定と、その結果を生かした効果の高い研修を実施したいとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
目次
研修の効果測定とは
研修の効果測定とは、研修によって生み出された成果を「見える化」し、研修目標の達成度を確認することです。その研修を継続して実施するべきか、改善すべき点はどこかといった検証をするために行われます。
研修担当者の中には、「効果測定は難しいイメージがある」、「どうしても必要なのか?」という方もいるでしょう。まずはこれらについて確認していきましょう。
研修の効果測定はなぜ難しい?
研修の効果測定が難しいといわれるのはなぜでしょうか。主な理由をいくつか挙げてみます。
- 評価基準が明確でない
- テーマによっては効果が抽象的になる
- 研修の効果が出るまでに時間がかかる
- 従業員やその上司が協力してくれない
- スキルアップがどの程度業務に貢献しているのかが不明
例えば、資格取得やマニュアルの理解といった、研修の前後で結果がある程度はっきりするテーマであれば効果測定はしやすいでしょう。
一方、近年注目されている、コミュニケーション力、マネジメント力、論理的思考力といったソフトスキルについては、スキルが身に付いたといえる明確な基準はありません。
自社で評価基準を定めたり、研修によってどの程度業務の質が向上したかを評価したりする手間がかかるため、十分な効果測定ができていないケースもあるようです。
実際に、HR総研の調査では、中堅社員研修の運営課題について「実施効果の測定ができていない」が39%で最多となっています[1]。
しかし、研修の効果を問われた際、経営層や管理職、一般の従業員が納得できる成果を示さなければ、今後、研修を含む人材育成施策に協力を得られない可能性もあります。そうならないために、効果測定は不可欠なのです。
さらに、社会的な背景からも研修の効果測定の需要は高まっています。次の項目で詳しく見てみましょう。
研修の効果測定を実施すべき理由
研修の効果測定は、以下のような社会的な背景から必要性が高まっています。
ビジネス環境の変化
大きく三つの変化が挙げられます。一つ目は雇用の流動化です。従来は終身雇用制度を前提に、人材への投資を長期にわたって回収しようとしていました。しかし雇用の流動化によってその手法は通用しなくなっています。
二つ目は生産性の低さです。日本生産性本部が公表した「労働生産性の国際比較 2023」[2]によると、日本の時間当たり労働生産性は52.3ドル(5,099円/購買力平価(PPP)換算)で、OECD加盟38カ国中30位でした。データが取得可能な1970年以降、最も低い順位となっています。研修の効果を高め、生産性向上を図る必要があるのです。
三つ目は、長期的な経済低迷により、企業が全社的なコストカットを行っていることです。研修については、単純に量を減らすのではなく、費用対効果が高いものに絞ろうという動きがあります。
このような変化が、「効果的な研修とは?」、「研修の成果を見える化するには?」という課題への関心を高めています。
研修方法やテーマの多様化
コロナ禍以降、eラーニングやウェビナーといったオンライン研修が広まりました。オンライン研修には運用やコストの面で多くのメリットがありますが、集合研修にはなかった以下のような課題もあります。
- 受講者同士の交流が減りがちである
- 個別のフォローがしにくい
- 実技の習得には不向き
そのため、集合研修と同様の効果測定では正確な結果を得られません。オンライン研修の特徴を踏まえた内容や方法の検討が必要です。
また、研修テーマも多岐にわたっています。DXやダイバーシティ、メンタルヘルスケアなど、社会の変化に合わせて習得しなければならないスキルも増えてきました。
研修方法とテーマの組み合わせによって到達目標や評価基準は複雑に変化するため、効果測定もさまざまな方法を組み合わせ、個々の研修に適した内容で行う必要があります。
関連 ▶ オンライン研修(Web研修)とは?導入のメリットとデメリット、成功させるポイント(弊社eラーニングサービスサイトへ移動します)
人的資本の情報開示の義務化
「人的資本」とは、従業員を自社の資本と捉える考え方です。従業員という資本に投資し、その価値を最大限に引き出すことで企業価値の向上を図る経営手法は、「人的資本経営」と呼ばれ注目されています。
そして日本では、2023年3月期から、有価証券報告書を発行する大企業に人的資本の情報開示が義務付けられました。
従業員への投資、つまり、人材育成・教育・研修にどれだけ費用や時間をかけたか、どのような実績を得たのかを開示しなければならないため、研修の成果を見える化する効果測定は不可欠なのです。
研修の効果測定を行う五つのメリット
研修の効果測定には、以下のようなメリットがあります。
研修予算の充実
経営層に対して、効果測定による明確な研修の成果を示せば、「研修は効果がある」との認識が浸透し、研修予算の獲得につながります。
ポイントは、研修にかかる費用をコストではなく、売上アップや生産性向上などリターンのある投資として捉えてもらうことです。
研修内容の改善
効果測定によって研修の成果や課題が明確になるため、研修の運営方法やプログラムの改善が可能です。
例えば、以下のような改善が考えられます。
- 受講者の理解度テストの成績がいまいちだった ⇒ 講師の説明やテキストの見直し
- 研修の後半は受講者の集中力が途切れがちだった ⇒ 研修時間の短縮
- グループワークが現場の課題解決につながった ⇒ グループワークを中心とした研修の増加
指導側の従業員の意識向上
効果測定によって、人事部員や管理職が企画者・講師として関わった研修の評価が明確になります。
効果測定の結果が良ければ、「やりがい」が向上し、研修業務へのモチベーションアップが期待できます。
「やりっぱなし」の防止
どれほど質の高い研修を実施しても、「やりっぱなし」にしてしまうと、研修の効果は時間が経つにつれて薄れてしまいます。
効果測定により、研修の実施⇒成果の見える化⇒より高い効果を得るための改善というサイクルが促進され「やりっぱなし」を防止します。
学習の進捗管理
研修の効果測定の結果を従業員一人一人にフィードバックすることにより、研修テーマに関する習熟度や課題を、管理職や従業員自身が認識できます。
従業員が目標達成プロセスのどの位置にいるかが把握でき、目標達成に向けた次のアクションを検討する際の参考にすることができます。
LMS(Learning Management System:学習管理システム)など、研修・学習を管理するシステムを利用すると効率的な管理が可能です。
目標達成に必要なスキルと学習を効率的に管理! ⇒ 「CAREERSHIP」のスキル管理機能を詳しく見る
研修の効果測定の基本:カークパトリックの4段階評価
「カークパトリックの4段階評価」は、米国の経営学者であるカークパトリック博士が提唱した、研修や教育の評価手法をまとめたモデルです。研修の効果測定の基本的な方法として広く知られています。
このモデルでは研修の評価を以下の4段階で行い、レベルが上がるごとに評価の難易度が高くなります。
- レベル1:リアクション(Reaction)
- レベル2:ラーニング(Learning)
- レベル3:ビヘイビア(Behavior)
- レベル4:リザルツ(Results)
レベル1:リアクション(Reaction)
レベル1では、受講者の反応を評価指標とします。
研修直後にアンケートやインタビューを実施し、研修がどの程度好意的に捉えられているかを、満足度や自由記述の感想から調査します。
レベル2:ラーニング(Learning)
レベル2では、研修で学んだ内容の理解度を評価指標とします。
理解度テストや実技試験、レポートなどを実施し、知識やスキルの習得レベルを調査します。研修当日~数日以内に行うと良いでしょう。
満足度の高い研修であっても、研修内容が身に付いていなければ業務に生かせないため、しっかりと習得度を測る必要があります。
レベル3:ビヘイビア(Behavior)
レベル3では、受講者の行動変容を評価指標とします。
受講者が職場に戻り、研修で学んだ内容を業務に生かしているか、本人や上司、同僚などにアンケートやインタビューを実施し多面的に評価します。研修実施後、ある程度の期間、例えば1カ月~1年程度を設定し、その期間の実践度合いを評価します。
研修の満足度が高く、学んだ内容が身に付いていても、実際の行動に結びつかなければ研修を実施した価値がなくなってしまいます。行動変容の評価は大変重要なポイントです。
レベル4:リザルツ(Results)
レベル4では、研修が企業の業績に与えた成果を評価指標とします。
研修の成果が業績に影響を与えるまでには時間がかかるため、研修後、6カ月~1年程度経過後に評価するのがよいでしょう。比較的簡単な方法として以下の二つがあります。
(1)KPI (Key Performance Indicator:重要業績評価指標)の変化の測定
例えば、営業の研修であれば新規顧客数やクレーム数、接客の研修であれば来店客数や平均客単価などを評価する。
(2)研修の受講者と非受講者の比較
研修の受講者と非受講者の業績の差を比較する。ただし、業績が向上する要素は研修だけではないため、複数のデータを用意し信頼性を高めることが望ましい。
また、難易度が高い方法ですが、ROI分析(後述)もレベル4の測定に有効です。
以上が、カークパトリックの4段階評価による研修の効果測定の方法です。なお、この4段階評価に新たな測定項目を追加し、5段階評価で効果測定を行うモデルも存在します。詳細は以下の関連記事をご確認ください。
関連 ▶ フィリップスのROIモデルとは 研修効果測定の5段階を解説(弊社ブログサイトへ移動します)
研修の効果測定の方法や指標
ここでは、研修の効果測定の方法や指標についてさらに詳しく見ていきましょう。以下の五つが効果測定によく用いられます。
アンケート
アンケートは、研修の効果測定の方法として最もポピュラーで簡単な方法といってよいでしょう。
アンケートでは、受講者に研修の内容、講師、教材などの満足度について5段階評価で尋ねる他、自由記述の感想を求めることで有用なフィードバックを得られます。
フィードバックの結果を受け、例えば、研修内容が好評であれば研修回数を増加する、講師が不評であれば変更するなど、より満足度を高めるための改善策を打つことができます。
アンケートの具体的な質問項目としては、以下のようなものが挙げられます。
- 講師の説明は分かりやすかったか
- 研修時間はちょうどよかったか
- 研修の内容を業務で生かせそうか
- 研修で得られた成果はどのようなものか
インタビュー
インタビューは、研修でどのような学びを得たか、業務に生かせそうかなどを直接受講者に尋ねる方法です。質問項目はアンケートと同様で構いませんが、研修前後の気持ちや行動の変化を引き出せるよう工夫が必要です。
なお、受講者がインタビュアーに与える印象を気にして、ネガティブな感想を控えてしまう場合があります。本音を引き出すためにも、人事評価には影響しないこと、研修の改善のために率直な意見が欲しいことなどを説明し、話しやすい雰囲気をつくりましょう。
テスト・レポート
テストは、受講者が研修内容をどれくらい理解したかを確認するものです。研修前にもテストを実施しておくと、研修前後の変化を測ることができます。
一般的な理解度テストは、筆記試験のほか、eラーニングのシステムで配信することもできます。その他、接客・技術の実技試験や資格試験の受検などもあります。レポートも理解度や習熟度を確認する手段として有効です。
行動観察
受講者の行動が研修によってどのように変化したかを、上司や同僚が評価します。
具体的には、受講者の業務の進め方や成果等についてアンケートを作成し、研修の前と後に上司や同僚に回答してもらうことで変化を確認します。
アンケートの質問項目は、回答者の負担にならないよう10問程度にまとめるとよいでしょう。
ROI分析
ROI(Return On Investment:投資収益率)とは、研修への投資額に対してどの程度の利益があったか(投資対効果)を測る指標のことです。
基本的な計算式は、「ROI(%)=研修によって生じた利益÷研修への投資額×100」で、数値が高いほど効率よく研修を実施できていることになります。
ROI分析はレベル4の効果測定に活用できますが、研修で生じた利益に影響している要素は何か、どこまで研修費用として計上するかなど複雑で難しい判断が求められる、難易度が高い方法です。そのため、社内でも重要度の高い研修のみROI分析を行うケースもあります。
LMS(学習管理システム)を活用して効果測定を効率化する
LMS(Learning Management System:学習管理システム)を活用すれば、研修の効果測定をより効率化できます。
例えば、当社の統合型LMS「CAREERSHIP」には、効果測定に役立つ機能として次のようなものがあります。
- 研修管理
- eラーニング
- コース管理(研修、eラーニング、アンケート等をまとめて管理)
- アンケート/レポート作成
- メール配信 など
研修管理機能では、従業員の研修参加予定や成績を一覧で把握できます。コース管理機能と組み合わせれば、課題の不合格者にのみリマインドメールを一斉送信し、期日までの再受検を促すといったことも簡単な操作で行えます。
事務負担を大幅に削減! ⇒ 「CAREERSHIP」の研修管理機能を詳しく見る
研修前後の理解度テストやアンケートも、作成・配布・回答・採点まで全てシステム上で完結するため、非常にスピーディーです。
このように、LMSの活用によって研修運営や効果測定にかかる手間や人手を大幅に削減し、テスト・アンケートの結果分析や改善施策の検討等、重要な部分に時間を割くことができます。
回答結果を自動集計! ⇒ 「CAREERSHIP」のアンケート機能を詳しく見る
研修の効果測定で意識すべき五つのポイント
研修の効果測定を行う上で、押さえておきたいポイントを五つご紹介します。
研修ニーズと研修内容を一致させる
効果の高い研修を実施するには、その研修が従業員のニーズを満たすものであることが重要です。米国の教育学者であるノールズが提唱した理論では、成人の学習者は、学習に対して問題解決に直結する要素を求めると考えられています。
研修のニーズは、業務上の課題を解決するという従業員の短期的なニーズだけではありません。経営層の、経営戦略に基づいた長期的な人材育成のニーズもあります。
このような、従業員にとって直接的なニーズが薄いテーマで研修を実施する場合には、日常業務とのつながりを明示し、研修の必要性を認識してもらうことが重要です。
従業員と組織の研修ニーズを把握するには、アンケートやインタビューを活用しましょう。ニーズに合わせた研修を実施することで、満足度や理解度の向上が期待できます。
研修の目標と効果測定の目的を明確化する
適切な研修準備や効果測定方法の選択のため、以下のような点を事前に明確化しておきましょう。
- 研修ではどのレベルを目指すのか
- 内容の分かりやすさなど研修そのものを評価するのか、行動変容が見られたかなど研修の成果を評価するのか
- 従業員、彼らの上司、経営層など、誰の立場で評価するのか
例えば、カークパトリックの4段階評価のレベル1、「満足度を高める」レベルを目指すなら、従業員が楽しめる、イベント要素の強い研修でもOKでしょう。受講者の満足度が高ければ、その研修は成功ということです。
しかし、レベル3の「行動変容を起こす」レベルを目指すのであれば、満足度が高いだけでは不十分です。
理解度を高める内容、ふさわしい講師、分かりやすい教材の作成、行動変容を促す現場のサポート等、事前に細かい部分まで綿密に検討しなければなりません。研修後は受講者だけでなく、その上司や同僚の立場からも行動変容が見られたか評価する必要があります。
測定可能な定量・定性目標を設定する
研修の目標は、研修の実施によって達成でき、効果測定が可能な定量・定性的なものであることが重要です。研修テーマや従業員の現状のスキルにそぐわない目標を設定すると、効果測定で得たデータの実用性が失われてしまいます。
まず定量目標とは、目指す状態を数値化した目標のことです。例えば以下のようなものが挙げられます。
- 研修後の理解度テストの合格率70%
- 1カ月後に商談数20件増加
- ROIで100%(投資額と同等の利益)を超える
対して定性目標とは、数値化できない目標のことです。以下のように、主に意識や行動の変化に関するものになります。定性目標の評価は、評価基準と点数を設定し行うのが一般的です。
- 周囲とのコミュニケーションの活性化
- お客様対応のブラッシュアップ
- 業務での主体性の向上
上司の協力を得る
研修と効果測定の実施について、受講者の上司の協力を得られるよう周知や説明を丁寧に行います。
上司が部下の研修の必要性を理解すれば、研修後、学んだ内容を業務に生かすサポートが期待でき、行動変容をスムーズに促進することにつながります。
「研修で良い結果を出し現場から良い評価を得る」よりも、「現場の協力を得て良い研修結果を出す」ことを重視し、研修実施⇒効果測定⇒改善のサイクルの質を高めましょう。
経営層の関心を高める
現場の上司だけでなく、経営層の関与も強めましょう。
経営層が人材育成への関心が高く、日頃から環境整備や成果の向上に注力している状態なら問題ありません。しかし、そうでない場合は経営層の動きが鈍く、その下に就く管理職、現場リーダー等も同様で、研修や効果測定への協力が得にくいことが予想されます。
研修担当者は、経営層に自社の従業員のスキルマップの提示をするなどして人材育成への関心を高め、必要性をよく理解してもらいましょう。研修や効果測定の変革は、組織ぐるみの取り組みが欠かせません。
研修効果の「見える化」成功事例
最後に、研修効果の「見える化」に成功した2社の事例をご紹介します。ぜひ参考にしてください。
株式会社JTB
国内最大手の旅行会社である株式会社JTBでは、従業員の研修に対する満足度は高いものの意識・行動変容にはつながらないという課題があり、研修改革に取り組み始めました。
同社の研修の効果測定における「行動変容の見える化」は、学習の到達状況を評価する基準であるルーブリック評価をヒントに、同社独自のレッスンルーブリックを作成し評価することとしました。
さらに、研修アンケートの大幅な見直しを行いました。満足度を尋ねるとほとんどの従業員が選ぶ「概ね満足」という回答を避けるため、研修前の期待値(期待していた/していなかった等)と研修後の期待値(期待以上だった/期待外れだった等)を尋ねます。
そして、行動変容の兆しを確認するための「職場に戻ってからの行動がイメージできますか?」という質問を加えました。
これらの見直しによって、次のことが分かりました。
・「職場に戻ってからのイメージが『十分できている』」人ほど自己効力感が高まり、職場に戻って行動変容を起こしやすい
・研修への期待値が高い状態で研修を受講すれば十分に行動イメージができ、研修後の行動変容につながりやすい
研修前の期待値を上げる鍵と考えられているのが、キャリア開発です。同社は従業員が理想のビジョンの実現のために自身で必要な学習を考え、自分への期待値を高められる状態を目指し、キャリア自律のためのさまざまな施策を実施しています。
キリンホールディングス株式会社
大手飲料メーカーのキリンホールディングス株式会社では、多様性の理解の推進施策として「なりキリンママ・パパ」という、育児や介護など時間に制約がある従業員の働き方を体験する研修を行っています。
研修では「育児」「介護」「家族の病気」の三つのシチュエーションから一つを選択し、1カ月の模擬体験をした後にレポートを提出、3カ月後に効果測定を行います。
実際の効果測定の結果、以下のように、定量的・定性的、双方の指標における成果が確認できました。
・定量的項目
所定外労働時間:2018年2月から6月の先行実施で約6割削減し生産性向上を実現[3]
・定性的項目
研修実施前と比べて以下の点が改善[4]:
- 他者を理解し、相互に支えあう意識
- 時間制約のあるメンバーを持った場合の対応やマネジメント
- リーダーや仲間への業務進捗等の開示・共有・巻き込み
- 将来の育児や介護、パートナーの病気など、時間制約のある働き方が起こり得ることへの不安解消
研修の参加者は制約のある従業員に対する理解が深まり、より的確なサポートが可能になったほか、職場で従業員同士が業務の状態を共有する習慣ができ、効率性への意識も高まったということです。
まとめ
研修の効果測定とは、研修によって生み出された成果を「見える化」し、研修目標の達成度を確認することです。その研修を継続して実施するべきか、改善すべき点はどこかといった検証をするために行われます。
研修の効果測定が難しいといわれる主な理由は以下の通りです。
- 評価基準が明確でない
- テーマによっては効果が抽象的になる
- 研修の効果が出るまでに時間がかかる
- 従業員やその上司が協力してくれない
- スキルアップがどの程度業務に貢献しているのかが不明
研修の効果測定は、以下のような社会的な背景から必要性が高まっています。
- ビジネス環境の変化
- 研修方法やテーマの多様化
- 人的資本の情報開示の義務化
研修の効果測定には、以下のようなメリットがあります。
- 研修予算の充実
- 研修内容の改善
- 指導側の従業員の意識向上
- 「やりっぱなし」の防止
- 学習の進捗管理
研修の効果測定の基本的な方法として、「カークパトリックの4段階評価」があります。研修の評価を以下の4段階で行い、レベルが上がるごとに評価の難易度が高くなります。
- レベル1:リアクション(Reaction)
- レベル2:ラーニング(Learning)
- レベル3:ビヘイビア(Behavior)
- レベル4:リザルツ(Results)
よく用いられる研修の効果測定のツールとして、以下の五つが挙げられます。
- アンケート
- インタビュー
- テスト・レポート
- 行動観察
- ROI分析
LMS(Learning Management System:学習管理システム)の以下の機能を活用すれば、研修の効果測定をより効率的に行うことができます。
- 研修管理
- eラーニング
- コース管理(研修、eラーニング、アンケート等をまとめて管理)
- アンケート/レポート作成
- メール配信
研修の効果測定を行う上で、押さえておきたいポイントは以下の五つです。
- 研修ニーズと研修内容を一致させる
- 研修の目標と効果測定の目的を明確化する
- 測定可能な定量・定性目標を設定する
- 上司の協力を得る
- 経営層の関心を高める
最後に、研修効果の「見える化」に成功した2社の事例をご紹介しました。
- 株式会社JTB
- キリンホールディングス株式会社
適切な効果測定が、効果の高い研修の実施につながります。貴社の人材育成の促進のため、この記事をお役立ていただければ幸いです。
[1] ProFuture株式会社/HR総研「HR総研:人材育成「中堅社員研修・管理職研修」に関するアンケート調査 結果報告」,『HRpro』, (閲覧日:2024年10月10日)
[2] 公益財団法人 日本生産性本部「労働生産性の国際比較2023」, (閲覧日:2024年7月1日)
[3] キリンホールディングス株式会社「『なりキリンママ・パパ』の展開部門拡大について」, (閲覧日:2024年7月26日)
[4] メトロポリターナトーキョー「《多様性に取り組む企業が目指す未来 2》キリンホールディングス:勤務の制約体験を通じて働く意識を変える[相互理解の現在地]」, (閲覧日:2024年7月26日)
参考)
茅切伸明、松下直子「研修効果測定の方法~どう『見える化』するか」,『PHP人材開発』, https://hrd.php.co.jp/hr-strategy/hrm/post-698.php(閲覧日:2024年7月26日)
アルー株式会社「研修効果測定の方法とは|4つの評価レベルや効果測定のポイント」, https://service.alue.co.jp/blog/training-effect-measurement(閲覧日:2024年7月26日)
KIYOラーニング株式会社「研修の効果測定方法|4つの評価レベルと段階別の測定手法を解説」, 『AirCourse人材育成サポーター』, https://aircourse.com/jinsapo/measuring_training_effectiveness.html(閲覧日:2024年
7月26日)
職業能力開発総合大学校 能力開発研究センター「公共能力開発施設の行う訓練効果測定 -訓練効果測定に関する調査・研究-」,『調査研究資料』,第114号, 2005.
小薗修「効果的な社員研修についての考察」,『経営戦略研究』,第2号, 2008, P133-144.
株式会社リクルートマネジメントソリューションズ「人事になったら知っておきたい10のこと 第9回『教育体系と研修の効果測定について知りたいです』」, https://www.recruit-ms.co.jp/issue/column/0000000908/(閲覧日:2024年7月26日)
エン・ジャパン株式会社「研修の効果を測定する『カークパトリックの4段階評価法』」,『エンカレッジ』, https://en-college.en-japan.com/column/2020/686/(閲覧日:2024年7月26日)
株式会社ヒューマンバリュー「研修効果測定のノウハウ」, https://www.humanvalue.co.jp/wwd/research/insights/articles/post_3/(閲覧日:2024年7月26日)
武田 安恵「子どもが急病……キリン社員は模擬体験 子育て支援のカギは 「当事者目線」にあり」,『日経ビジネス』, https://business.nikkei.com/atcl/NBD/19/special/01264/(閲覧日:2024年10月9日)