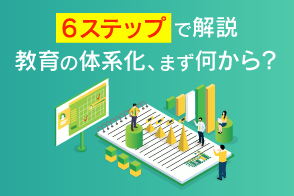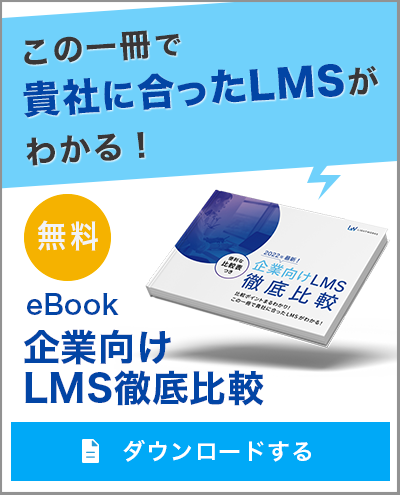研修の課題を解決!教育の質や効果測定を高める方法、企業事例を解説
最終更新日:
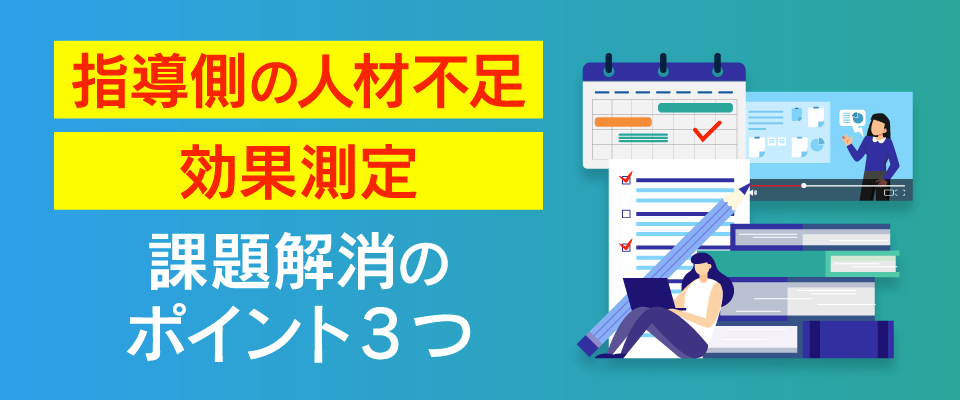
「社内研修の効果がわかりづらい。課題感はあるが、どこから解決すればよいだろう?」
コストや時間をかけて研修を行う以上は、有意義なものにしたいところです。しかし現実には、研修を受講させても効果が見えない、満足な質の指導が行えていないなど、課題感を持つ企業も少なくないのではないでしょうか。
この記事では、研修運営で起こりがちな課題をさまざまな調査結果から整理し、企業事例も交えて解決の手がかりを探ります。特に、学習した内容を早期に業務で活用できるようにすること、指導側の負担や質のばらつきを抑えることについて、具体的な手立てを紹介します。
研修の課題解決の糸口を探しているという方は参考にしてみてください。
自動で研修の効果測定まで完了!⇒ CAREERSHIPのアンケート機能を詳しく見る
目次
企業の研修で起こりがちな課題とは
研修の課題にはどのようなものがあるでしょうか。ここでは近年行われたいくつかの調査を参考に、企業が抱える研修の課題について探ってみましょう。
社内で行う研修において課題になりがちなのが、指導する側に関する問題です。東京商工会議所による調査[1]では、Z世代の若手社員の指導・育成に関する企業としての課題として、以下のように指導役の不足に関する声が挙がっています。
- 業務繁忙等により、若手社員の指導・育成にかけられる時間が不足している…38.2%
- 若手社員が気軽に相談できるメンターやOJTの指導役となる社員がいない(不足している)…34.7%
- 若手社員を指導・育成しても会社をやめてしまう…32.8%
また、実施した研修の効果測定の面で課題を抱える企業も多いようです。HR総研による、管理職研修に関するアンケート調査[2]では、運営上の課題として効果測定に関する悩みがトップに挙がりました。
- 実施効果の測定ができていない…38%
- 受講者の意識…32%
- 研修メニューの構築・選択が困難…24%
研修の課題にはさまざまなものがありますが、人材の定着および業務での実践はどの企業にとっても重要といえます。一方で、研修運営に当たっては指導側の時間や人材の確保、効果測定が問題となる傾向がうかがえます。
研修における課題を整理
前章で紹介した調査結果を踏まえ、研修の課題を以下の3点に整理しました。
指導側のリソース/力量が不足している
OJTや社内講師による研修を主要な育成手段とする企業では、指導を引き受ける人材の不足は大きな課題です。指導役を担う従業員にしても、自身の業務がある中で指導に充てる時間を確保することは簡単ではないでしょう。そもそも、十分な指導力を持つ人材を必ずアサインできるとは限りません。
また、現場業務で忙しい環境でのOJTなどでは体系的な指導が難しい場合もあり、配属先や指導担当者による質のばらつきが懸念されます。
昨今は「OJTガチャ」「上司ガチャ」という言葉もあり、指導の質のばらつきに不安や不満を感じる人材が少なからずいると考えられます。企業としては、環境によって学びの質に差が出ることは避けたいものです。
学習したことを実践で生かせない
研修を受講してもその場限りの学習で終わってしまい、知識やマインドが定着しない、業務における実際の行動につながらないといった悩みもありがちです。
一因として、受講者自身がその研修内容を具体的にどう役立てればよいか分からないということが考えられます。例えば、研修内容が現在の所属やポジションと関連が薄い、業務での実践をイメージしづらいといったケースです。そうした状況では、研修を受講するモチベーションも保ちにくいでしょう。
また、研修で学んだことを現場で実践する環境が整っていない場合も考えられます。一例を挙げると、お客さま対応などの現場業務に追われ、学びを生かせているか、振り返る機会をなかなか持てないケースなどです。
本人任せにするだけで、学習の定着度合いをチェックする仕組みや上司を含めた周囲の理解がなければ学びを実践で生かすことは難しくなります。
効果測定ができていない
前節で述べたように、学んだことを行動に移し業務に活用できてこそ研修の成果があったといえるでしょう。しかし研修の効果測定において、この行動変容を測れていないケースが多く見られます。
一般的に効果測定として行われるのは、確認テストや研修後のアンケートが多いでしょう。しかし多くの場合、こうした手段は研修直後の理解度や研修の満足度を測るだけで、知識の定着度や業務での実践度合いを測定できるものではありません。
また、受講者が行動変容に至ったか調べるには期間を空けた調査が必要になることもありますが、研修の運営担当者が忙しく、そこまで手が回らないという事態も起こりがちです。
研修の課題を解決するポイント
こうした研修の課題を解決するには、どのようにアプローチすればよいでしょうか。ポイントを3つにまとめました。
研修の質の均一化
研修の質を安定させるために欠かせないことが、研修内容の共通化です。教えるべき内容を現場や指導担当者個人に任せるのではなく教材としてまとめると、過不足なく必要な指導内容を把握できるため指導の質のばらつきを抑えられるでしょう。指導担当者の負担軽減にも大きく役立ちます。
また、動画教材を用いた研修も効果的です。受講者それぞれが都合の良いときに視聴して学ぶ仕組みにすることで、必要な部分を繰り返し視聴するなど、個々の理解度に合わせた学習が可能です。
動画教材を制作する際は、画像やアニメーションを活用してイメージを視覚的に理解しやすくすると認識のズレを防ぐことができるでしょう。
教育の体系化
研修を効果的なものにするには、研修の目的を明らかにし、その達成に向けて計画的に実施することが不可欠です。指導担当者や研修運営にかかるリソースもあらかじめ計画に組み込み、過度な負担なく実施できるようにしましょう。
研修の目的は、経営目標や組織の人材育成方針を踏まえて設定します。そのため、組織として計画的に研修に取り組む体制の整備が必要です。キャリアパスに沿った研修体系が構築されれば、研修を受けるメリットや目標が明確になり、従業員のモチベーション向上にもつながります。
適切な効果測定
研修の目的の明確化は、同時に、何を効果として測るべきかを具体化することでもあります。繰り返し述べてきたように、学んだことが定着し業務で実践されてこそ、研修の成果があったといえるでしょう。
つまり効果として測定すべきは研修後の行動変容であり、研修の目的が達成されたかを客観的にチェックする仕組みが必要です。
そのためには、研修の終わりに行うアンケートだけでは十分ではありません。業務での実践状況を調査するには、数カ月など期間をおいての追跡調査や、本人だけでなく上司をはじめ周囲の人からの客観的な意見の収集が効果的です。
一例として、ライトワークスのLMS(学習管理システム)CAREERSHIPでは、研修の実施と修了テスト、本人アンケート、上司へのアンケートなどを組み合わせ、研修から効果測定までの施策を自動配信として設定することが可能です。
自動で研修の効果測定まで完了!⇒ CAREERSHIPのアンケート機能を詳しく見る
研修課題に向き合う企業事例
最後に、研修方法を見直し教育の均質化・体系化を実現したことで、新入社員教育の課題解決に取り組んだ企業の事例を紹介します。
店舗物件の転貸借事業を展開する株式会社テンポイノベーションは、新入社員の定着率向上と研修担当者の負担軽減を目指し、研修方法の見直しを行いました。
背景には、不動産業の営業は専門知識を要し、業務も多岐にわたるため、新入社員が独力で契約成立までのプロセスに対応できるまでに2~3年かかってしまうという課題がありました。
なかなか成果が出せず心が折れてしまうことから起こる早期離職を避けるべく、一人前になるまでの期間を短くするための取り組みが必要になったのです。
加えて、研修担当者にかかる負担の大きさも課題でした。研修は入社時期に応じてチームごとに実施され、各チームに対し約100時間を費やしていたといいます。
研修担当者は、新入社員への研修を実施しながら、チーム内でのOJTやチームメンバーのサポートを担い、自身も業務において成果を上げなければならず、過大な負担がかかっていました。
このような中で同社が取った解決方法は、研修内容を動画教材に集約し、研修を体系化するというものです。社内に分散していたナレッジを整理し、約300本の動画教材が作られました。研修の質を高いレベルで均一化でき、アニメーション動画でイメージの行き違いや説明コストも激減しました。
受講者は視聴プログラムに沿ってテーマごとに複数の動画を視聴し、その都度、研修担当者との1on1で理解度チェックとフィードバックを受けるという流れで学習を進めます。これにより研修担当者の負担は大きく軽減され、新入社員のサポートやケアを手厚く実施できるようになりました。
こうした取り組みの結果、新入社員が早期に成果を上げ、自信を持って業務に当たれるようになったことで早期退職を防止できているといいます。
同社が「人材育成の基礎を築けた」とする動画教材の導入を支えたのは、ライトワークスのeラーニング教材制作サービスです。制作スピードに加え、丁寧なヒアリングで専門的な研修内容を分かりやすい表現に落とし込む教材制作力、制作中の手厚いサポートが高く評価されています。
自社オリジナル教材をスピーディーに制作!⇒ eラーニング教材制作サービスを詳しく見る
まとめ
企業の研修において重要視されることは、学んだスキル・知識の業務での活用、そして人材の定着ではないでしょうか。しかし実際には、指導側の人材不足、学びが実践につながらない、実施効果の測定ができていないといった課題から、研修を行っても思うように効果が上がらないという声が聞かれます。
こうした課題に対し、解決のためのアプローチを3つのポイントにまとめて解説しました。
1つめは研修の質の均一化です。研修内容を教材化することで、指導の質のばらつきと指導担当者の負担を抑えることができます。動画教材を用いた研修も効果的です。
2つめは教育の体系化です。効果的な研修にするには、目的に沿って計画的に実施することが重要です。経営目標や人材育成方針を踏まえて研修の目的を明らかにし、キャリアパスに沿った研修体系を構築しましょう。
受講者にとっても研修を受けるメリットや目標が明確になり、モチベーション向上につながります。
3つめは適切な効果測定です。研修の目的を明確にすることで、実施効果として測定すべきものも具体化できます。学んだ知識・スキルが定着し業務で実践できるようになったか、行動変容を測る仕組みを設けましょう。期間をおいての調査や、上司を含め周囲の人へのアンケートなどが考えられます。
最後に、動画教材の導入による教育の均質化・体系化に取り組み、新入社員の早期戦力化および早期離職防止に成功した企業事例を紹介しました。研修担当者の負担も大幅に軽減され、新入社員のサポートやケアに時間を割けるようになったといいます。
研修をより効果的なものにするためには、現状の課題を明らかにし、それぞれに合ったアプローチが必要です。この記事が課題解決の一助になれば幸いです。
[1] 東京商工会議所「企業の人材育成担当者による新入社員・若手社員に対する意識調査 集計結果」,2024年4月22日公表,P9,(閲覧日:2024年11月5日)
[2] HR総研「HR総研:人材育成「管理職研修」に関するアンケート調査 結果報告」,『HR Pro』, (閲覧日: 2024年11月5日)