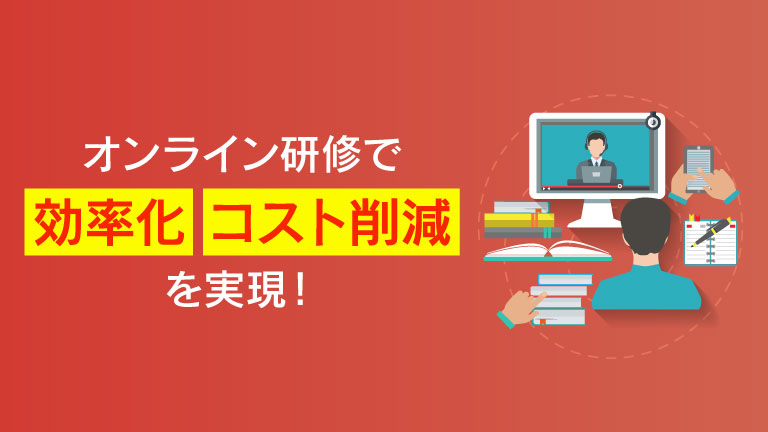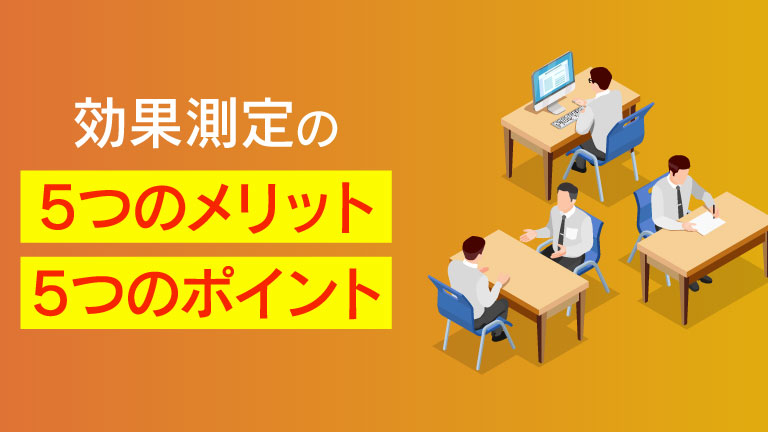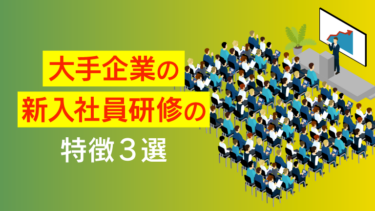「新入社員研修をオンラインに移行したいが、研修の効果に影響はないだろうか?」
従来、新入社員研修といえば集合研修が当たり前でしたが、2020年以降は新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、多くの企業がオンライン研修へと移行しました。
オンライン研修は、会場費や交通費といったコストや人事部の事務負担を削減できるなどメリットも多く、現在も新入社員研修をオンライン化したり、eラーニングを取り入れたりする企業は一定数存在しています。
新入社員研修をオンライン化した結果、その成果が従来の集合研修を上回った企業もあります(この記事の6章で紹介)。オンライン化による効果減少を心配する方もいるかと思いますが、うまく取り入れれば十分な効果が見込めるのです。
この記事ではeラーニング導入の手順や、実施の注意点を解説します。また新入社員研修にeラー二ングを取り入れることでどのようなメリットが得られるのか、実際の企業の成功事例を交えて紹介します。ぜひ参考にしてください。
研修の実施実態・Z世代が求める研修内容とは?⇒「新入社員研修に関する調査結果」を無料DLする
なぜ今、新入社員研修のオンライン化が注目されるのか?
新入社員研修のオンライン化が注目される理由を見ていく前に、まずは新入社員研修の概要と、オンライン研修やeラーニングとはどのような学習スタイルなのかを確認しておきましょう。
新入社員研修の概要
新入社員研修とは、企業が新卒や中途採用で入社した従業員に対して行う研修のことです。業務や社風への早期適応と、業務で必要となる知識やスキルの習得を目的としています。
新入社員研修では、企業理念やビジョン、就業規則、ビジネスマナーといった基本的な内容に加え、コミュニケーションスキルなど、社会人として働く上で必要なスキル全般を学びます。また、配属された部署の業務に関する研修も行われます。
以前は集合研修が一般的でしたが、現在主流となっているのは、対面形式とオンライン形式をうまく組み合わせたハイブリッド型の新入社員研修です。
当社による2023年度の調査では、新入社員研修を対面形式とオンライン形式のハイブリッド型で開催する企業が35.8%となり、対面形式のみ(23.9%)とオンライン形式のみ(27.9%)のそれぞれを上回る結果となりました。
また、2024年度の新入社員研修実施予定について、23.4%が今後も「オンライン形式のみで実施」と回答しており、オンライン研修がある程度定着しているようです。
研修の実施実態・Z世代が求める研修内容とは?⇒「新入社員研修に関する調査結果」を無料DLする
オンライン研修/eラーニングとは?
オンライン研修は、インターネットを介して実施される研修のことです。大きく分けて以下の2種類があります。
| リアルタイム型(双方向型) | 講師や他の受講者とリアルタイムにコミュニケーションを 取りながら受講する形式 |
| オンデマンド型 | 学習コンテンツや講義・実技(接客例など)の動画を 自分のペースで視聴する形式 |
このうちリアルタイム型(双方向型)は、講師による講義をリアルタイムで配信し、受講者が自宅などで聴講するという、集合研修に比較的近い形式のオンライン研修です。
eラーニングは学習コンテンツや講義の録画などを視聴して個人で学習を進めていく方法で、オンデマンド型に分類されます。一般的なeラーニングシステムでは、テキストや動画などの教材の登録・配信、理解度テストの実施、学習進捗管理といった機能が利用可能です。
厚生労働省による2023年度の「能力開発基本調査」1では、正社員、正社員以外とも自己啓発の実施方法として「eラーニング(インターネット)による学習」を挙げる割合が最も多く、正社員43.6%、正社員以外41.2%という結果でした。
新入社員の学習意欲や満足度を高めるには、eラーニングの導入は効果的であるといえるでしょう。
新入社員研修のオンライン化が進んだ理由
新入社員研修のオンライン化が進んだ背景には、新型コロナウイルスの感染拡大が大きく影響しています。2020年以降、多くの企業が感染拡大防止のために従来の集合研修からオンライン研修へと移行せざるを得ない状況となりました。
実際にオンライン研修が実施されると、従来の集合研修に関するさまざまな課題が解決できるというメリットが注目されるようになりました。
例えば、集合研修では、新入社員を1カ所に集めるため時間や場所の制約が大きく、会場費や移動費などのコストも企業にとって大きな負担となっていました。オンライン研修であれば、新入社員がどこにいようとも同じ内容の研修を提供でき、会場費や移動費の削減もできます。
このように、コロナ禍をきっかけに多くの企業がオンライン研修を導入し、その有効性が確認されたことで、新入社員研修のオンライン化やeラーニングの活用がある程度定着したと考えられます。
新入社員研修にeラーニングを取り入れるメリット
新入社員研修にeラーニングを取り入れると、具体的にどのようなメリットが得られるでしょうか。ここでは新入社員側と企業側、2つの視点で解説していきます。
新入社員側のメリット
幅広い内容を効率的に学習できる
新入社員研修では、企業理念やビジネスマナー、業務に必要なスキル、コンプライアンスなど、多岐にわたる内容を限られた期間で学習しなければなりません。
新入社員研修の全てが集合研修で実施されるのではなく、適度にeラーニングが取り入れられていれば、新入社員個々が都合の良い時間・場所で学習を進めることができ、効率的な学びが期待できます。
学びのハードルを下げられる
社会に出たばかりの新入社員は、働く上で必要な知識やスキルを学ぶことに慣れていません。まずは学びに対する心理的なハードルを下げる必要があります。
eラーニングで動画やクイズなどのコンテンツに楽しみながら触れることで、新入社員でも学習に取り組みやすくなるでしょう。
関連 ▶ 面白い新人研修を企画するポイント!事例や研修内容のヒントを紹介
自分のペースで学習できる
eラーニングでは、一度学習した内容を繰り返し学習することができます。一度で理解できなくても、自分のペースで繰り返し学習し、理解を深めることができるのです。それにより、学習効果の向上が期待できます。
また、大勢で一斉に受講する集合研修では緊張してしまったり、周りのペースについていけなかったりする新入社員もいるかもしれません。しかし、eラーニングであれば、リラックスした状態で、自分のペースで学習を進めることができます。
学習習慣が身に付く
社会人になると学生時代と比べて自由時間が減り、学習時間の確保が難しくなります。しかし、eラーニングという手軽な学習手段があれば、隙間時間などを活用して継続的な学習が可能です。
特に新入社員の頃からeラーニングに慣れ親しむと、学習が習慣化され、仕事の合間に学ぶことへの抵抗感も薄まるでしょう。
自律的成長を続ける「学び上手なひと」を目指す⇒ Learning Hacker「スタディハックシリーズ」コースを詳しく見る
企業側のメリット
学習の進捗状況を把握できる
従来の集合研修では個々の学習の進捗や理解度を把握することが難しく、研修修了後に十分な知識やスキルが身に付いていない新入社員がいても見落とされる場合もありました。その点、多くのeラーニングシステムでは従業員一人一人の学習の進捗や成績を容易に確認できます。
特に新入社員研修においては、ビジネスマナーやコンプライアンスといった多様なテーマがあるため、誰がどれを修了したか、理解度テストの成績はどうだったかなどを把握することが重要です。
さらに理解度テストの成績データに基づいて個別にフォローアップを行えば、全ての新入社員の研修成果を一定のレベルに均一化することにつながります。
研修のコストと工数が削減できる
eラーニングを導入することで、従来の集合研修に比べて、会場費や講師の交通費、宿泊費、研修資料の印刷費などのコストを大幅に削減できます。
さらに、eラーニングは一度教材を作成してしまえば、何度でも繰り返し利用することができ、内容の変更や改善も簡単です。そのためシステムの導入費用を考慮しても、長期的な視点で見れば費用対効果が高いといえるでしょう。
また、研修の実施にかかる時間や労力も軽減できるため、新入社員育成を担う人事担当者の負担を減らすことが可能です。
研修の実施実態・Z世代が求める研修内容とは?⇒「新入社員研修に関する調査結果」を無料DLする
新入社員研修でのeラーニング導入手順
次に、実際に新入社員研修にeラーニングを導入するための手順を見ていきましょう。
目的・目標の設定
新入社員研修へのeラーニング導入の成否は、目的と目標の明確な設定にかかっています。
目標の例としては、ビジネスマナーの習得を目的とする場合、「電話対応などのビジネスマナーについてのeラーニング講座を受講し、ロールプレイングテストで全員が80点以上を取れるようになる」などが挙げられます。
目的や目標が明確でなければ実施後の効果測定が難しくなり、システムやカリキュラムの適切な改善につなげられず、eラーニングを導入する効果が薄れてしまいます。
研修内容設計
次は研修内容を具体的に設計していきます。3-1.で決めた目標を達成するために、どのような内容を、どのような順番で学ばせるのかを検討しましょう。
例えば、新入社員研修で「ビジネスマナー習得」を目的とする場合、以下のような内容・流れが考えられます。
| (1)社会人としての心構え | eラーニングで座学 |
| (2)電話対応 | eラーニングで動画視聴後、集合研修でロールプレイング |
| (3)名刺交換 | eラーニングで動画視聴後、集合研修で新入社員同士で実践 |
上記のように、電話対応や名刺交換といった実践することで身に付きやすい内容は、eラーニングと集合研修を組み合わせるとより効果的です。このように2種類の方法を組み合わせる学習をブレンディッド・ラーニングといいます。
関連 ▶ ブレンディッド・ラーニングとは 研修とeラーニングのうまい組合せ方
システムの選定
eラーニングを実施するプラットフォームとなる「eラーニングシステム」には、大きく分けてクラウド型とオンプレミス型の2つがあります。
クラウド型は、ベンダーが構築したシステムにインターネット経由でアクセスするタイプで、導入までの期間が比較的短く、初期費用を抑えられる点がメリットです。デメリットとしては、オンプレミス型に比べて独自のカスタマイズがしにくい点が挙げられます。
一方、オンプレミス型は、自社のサーバーにシステムを構築するタイプで、セキュリティレベルが高く、カスタマイズを自由に行える点がメリットです。しかし、クラウド型に比べると初期費用が高くなる傾向があります。
eラーニングシステムの選定は、自社のニーズや予算、IT環境などを考慮して決定しなくてはなりません。どのようなシステムを採用するかが、新入社員研修の効率や学習効果に大きく影響します。機能やコンテンツの比較ポイントは、次章で詳しく解説します。
社会で活躍するために必要な知識を習得させる⇒「新入社員研修」のeラーニング教材を詳しく見る
教材の選定・作成
eラーニングシステムは、大きく2つのタイプに分けられます。1つは、あらかじめ学習コンテンツが搭載されているタイプです。用意されている学習コンテンツを活用すれば、新入社員に必要な標準的な内容を学ばせることができ、企業側の事前準備も比較的簡単です。
もう1つは、学習コンテンツが搭載されていないタイプです。この場合は、自社の新入社員に必要な内容をカバーした学習コンテンツを購入または作成する必要があります。
ベンダーによっては、既存コンテンツの一部を自社の資料に差し替えるなどのカスタマイズや、自社の状況に即した内容にするために教材を一から作成することも可能です。より身近なリアリティのある内容で、自社の新入社員のニーズに応えることができます。
学習コンテンツは、新入社員のニーズや学習効果を考慮し、テキスト教材、動画教材、音声教材など、さまざまな形式の教材を組み合わせるとよいでしょう。
運用体制の構築
eラーニングを活用した新入社員研修では、システム運用に関わる各々の役割を明確にして、スムーズな運用体制を構築する必要があります。
例えば、システムの運用管理や問い合わせ対応を行う「運用責任者」、研修計画の作成や教材選定、進捗管理を行う「研修担当者」、実際に新入社員と接して質疑応答や学習サポートを担う「指導者」といった役割が挙げられます。
また、新入社員の学習状況や課題を早期に把握し、必要なサポートを提供できるように、定期的なミーティングを行うなど、システム運用に関わるメンバー同士の連携を密にするようにしましょう。
効果測定・改善
研修修了後には効果測定を行い、結果に基づいて改善策を検討しましょう。効果測定では、事前に設定した研修の目的や目標の達成度合いを評価します。
eラーニングシステムの学習ログ・データなどを分析すれば、受講者の学習進捗状況や、つまずきやすいポイントなどを可視化することもできます。
このような効果測定の結果を基に、研修計画や教材の見直し、受講者へのサポート体制の強化など、具体的な改善策の立案が可能です。毎年新入社員研修を実施するたびに改善策を打ち出し、eラーニングの内容をブラッシュアップすることで、より効果的で質の高い研修の実現を目指します。
eラーニングシステムの比較ポイント
現在ではさまざまなeラーニングシステムが提供されているため、導入の際には複数のシステムをじっくり比較検討しなくてはなりません。ここではeラーニングシステムの比較ポイントを紹介します。
eラーニングシステムは、インターネットを通じてオンライン上で教材を配信するための […]…
コンテンツの充実度
eラーニングシステムを選ぶ際には、まず学習コンテンツの充実度を確認しましょう。
特に、教材作成にかかる時間やコストを抑えたい企業の場合は、ビジネスマナーや業界知識など、新入社員研修に必要なコンテンツがあらかじめ豊富に用意されている製品を選ぶことが重要です。
学習コンテンツが充実していれば、教材を作成する手間が省かれ、研修担当者の負担を最小限にして研修を実施できます。近年の汎用教材は質が高いものも多く、学習効果は十分に得られるでしょう。
教材のカスタマイズのしやすさ
eラーニングシステムにおいては、カスタマイズのしやすさも重要な比較ポイントです。特に、自社が保有する資料や講義の録画などの動画を、簡単に教材化してシステム上で配信できる機能は大きなメリットとなります。
これまでの新入社員研修(集合研修)で使用した資料を活用したい企業や、独自の新入社員研修計画がある企業などにとっては、学習コンテンツの充実度よりもカスタマイズ性の高さを優先する方が適しているケースもあるでしょう。
また、一から教材を作成する場合には、簡単に動画の作成や編集ができる機能を備えたeラーニングシステムもおすすめです。このような機能があれば、研修内容をタイムリーに変更したり、新入社員の理解度に合わせて教材の内容を調整したりすることが可能になります。
学習をサポートする機能
eラーニングシステムは、製品によって効率良く受講者の学習をサポートするためのさまざまな機能が搭載されています。例えば、以下のような機能があります。
| リマインド機能 | 学習の開始や課題提出期限などをメールで通知する機能 |
| 学習のロードマップ | 受講者の学習進捗や理解度に合わせて、 最適な学習経路を示す機能 |
| スキル管理機能 | 従業員一人一人に必要なスキルを表示する機能 |
| 理解度テスト | 学習内容の理解度を測るテストを自動で採点し、 間違えた箇所については解説を表示する機能 |
| アンケート/レポート提出 | アンケート配信や回答結果の自動集計を行う機能。 研修前後の課題提出にも活用できる |
| 掲示板機能(社内SNS) | 受講者同士や講師との間で、質問や意見交換が できる場を提供する機能 |
これらの機能は、ただ効率的に学習できるだけでなく、新入社員の学習意欲向上にもつながります。例えば、学習のロードマップや必要なスキルが示されれば、自身のステップアップが可視化され、達成感が得られることでモチベーションが高まるでしょう。
自社の新入社員研修の目標達成のためには、どのような機能があると効果的かを見極めて、eラーニングシステムを選定することが重要です。
費用対効果
eラーニングシステムを選ぶ際には、費用対効果を意識することが重要です。 一口にeラーニングシステムといっても、機能性には幅があります。高機能なシステムは魅力的ですが、費用も高額になりがちです。
例えば、豊富な学習コンテンツが魅力のeラーニングシステムでも、自社の新入社員研修で活用できるコンテンツは限られているかもしれません。また、高度なカスタマイズが可能でも、実際には標準機能で十分対応できたというケースも考えられるでしょう。
自社にとって本当に必要な機能を見極め、不要な部分にコストをかけずに済むよう選定することが費用対効果の最大化につながります。
新入社員研修でオンライン研修/eラーニング導入の際に注意すべき点
オンライン研修やeラーニングを導入すると高い学習効果が見込めますが、導入に際しては注意点もあります。ここでは、気を付けるべき4つのポイントを紹介します。
受講環境の整備
オンライン研修やeラーニングでは、インターネットに接続できる通信環境と、パソコンやタブレットなどのデバイスが必須です。新入社員の中には、eラーニングの受講が初めての人や、通信環境が不十分であったり、デバイスを所持していなかったりする人もいるでしょう。
新入社員の受講環境によって学習効果に差が出ないように、全ての受講者に対して環境を整える必要があります。具体的には、社内で学習できるスペースを設けたり、デバイスを貸与したりするなどの対策が考えられます。
企業側で事前に新入社員それぞれの受講環境を把握し、必要に応じてサポートを提供しましょう。
学びを実践する場の設置
eラーニングは、場所や時間に縛られずに学習できて便利な反面、受け身になりやすく、学習した内容が実践レベルまで定着しにくいという面も持っています。
そのため、eラーニングを導入する際には、新入社員が学んだことを実践できる場を設けるとよいでしょう。例えば、名刺交換や来客対応を動画などで学んだ後に、グループワーク、ロールプレイング、OJTなどを積極的に取り入れると、知識が定着しやすくなります。
実践の場を通して、新入社員は学んだ内容がスキルとして身に付いていることを実感でき、自信を持てるようになるでしょう。
受講者のモチベーション維持
eラーニングでは、集合研修のように講師・他の受講者と共に研修する緊張感や講師の判断によるペース配分の調整などはありません。そのため、学習が滞りなく進むように受講者のモチベーション維持が課題になります。
例えば、ゲーム要素を組み込んだり、達成度を可視化したりするなどの工夫を取り入れ、受講者の学習意欲をかき立てましょう。
学習にゲーム要素を組み込む方法として、成績に応じてポイントが付与される制度や、受講者同士の競争心を刺激するランキング表示などが挙げられます。
また達成度の可視化には、学習の進捗状況をグラフ化したり、目標達成に必要な学習時間や講義を表示したりするといった方法が効果的です。
質疑応答やコミュニケーションの機会確保
eラーニングは自宅などで一人で取り組む学習スタイルなので、新入社員が疑問点をすぐに聞けない、不安を感じやすいという課題もあります。定期的に面談やグループワークの機会を設け、講師や先輩従業員に気軽に質問や相談ができるようにすることが大切です。
また集合研修と違い、eラーニングでは新入社員同士の交流の機会が少なく、同期入社としての連帯感が育まれにくいというデメリットもあります。オンラインコミュニティやグループチャットなどを活用し、新入社員同士が気軽に交流できる場を提供しましょう。
社会で活躍するために必要な知識を習得させる⇒「新入社員研修」のeラーニング教材を詳しく見る
新入社員研修をオンライン研修/eラーニングで行う企業の事例
最後に、新入社員研修にオンライン研修やeラーニングを取り入れ、成果を上げている企業事例を2つ紹介します。
TOPPANホールディングス株式会社(旧:凸版印刷株式会社)
総合印刷会社のTOPPANホールディングス株式会社は、新型コロナウイルス感染対策として2020年度からオンラインでの新入社員研修を開始しました。
独自のプラットフォームで、従来の集合研修で蓄積された研修資料を活用した動画やライブ配信などを視聴して学ぶ仕組みになっています。
研修最終日に実施される総括アセスメント(総合テスト)においては、オンライン研修を実施した2020年度の最終スコア(平均)が95.9点となり、集合研修での数値を上回りました。この要因の1つとして、約76%の受講者がコンテンツを見直し、復習や反復学習を行っていたことが挙げられます2。
その他、終日座学が続くことによるパフォーマンス低下を防ぐために、コンディション管理に活用できる独自のアプリを導入したり、新入社員をネットワークでつなぎ、トレーナー役の先輩従業員を配置してコミュニケーションの促進を図ったりする施策も実施しました。
同社は2020年度以降も完全オンラインの新入社員研修を続けており、VRのオンライン研修センターやメタバース上での交流など、研修の充実と学習効果向上に取り組んでいます。
株式会社スポーツオアシス(旧:株式会社東急スポーツオアシス)
会員制フィットネスクラブなどを運営する株式会社スポーツオアシスでは、eラーニングを導入して効率的な教育体制の確立に成功しました。
以前の同社での新人教育は、大部分を各店舗でのOJTに委ねていました。しかしOJT担当の従業員は、指導の途中であっても必要があれば顧客応対に回ります。その間、指導は中断されてしまうため、新人スタッフのモチベーション低下につながるという状況が見られました。
そこで本社が中心となって、全店舗で共通して必要となる業務知識を体系的に学べるeラーニングシステムを導入し、eラーニングとOJTの2本柱で新人教育を進めることにしました。
すると、OJT担当の従業員が顧客対応のために指導を中断しても、新人スタッフはeラーニングに取り組んで学習を進められるようになりました。
OJT担当の従業員にとっても、eラーニングによってベースを作りOJTでしっかりと身に付けるという流れができたことで、新人スタッフの指導にかける時間や労力の削減につながりました。
その他eラーニング導入の効果として、新人教育の内容を整理し体系化することができた、学習の進捗や習熟度が可視化されて指導しやすくなったなどが挙げられています。
こちらの事例は、以下の記事で詳しくご覧いただけます。
店舗を運営する企業に共通する課題「新人教育を効果的・効率的に実施し、早期戦力化を実現していくこと」について、どのようにス…
研修の実施実態・Z世代が求める研修内容とは?⇒「新入社員研修に関する調査結果」を無料DLする
まとめ
新入社員研修とは、企業が新卒や中途採用で入社した従業員に対して行う研修のことです。
また、オンライン研修とはインターネットを介して実施される研修を指し、大きく分けてリアルタイム型(双方向型)とオンデマンド型があります。eラーニングはオンデマンド型に含まれる学習方法で、学習コンテンツや講義の録画などを視聴して個人で学習を進めます。
2020年以降、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、多くの企業で新入社員研修のオンライン化が進みました。それをきっかけに、オンライン研修の柔軟性やコスト面などのメリットが評価され、新しい研修スタイルとして定着しつつあります。
新入社員研修にeラーニングを取り入れると、新入社員側と企業側どちらにもメリットがあります。新入社員側のメリットは以下の通りです。
- 幅広い内容を効率的に学習できる
- 学びのハードルを下げられる
- 自分のペースで学習できる
- 学習習慣が身に付く
また、企業側には以下のようなメリットがあります。
- 学習の進捗状況を把握できる
- 研修のコストと工数が削減できる
新入社員研修でのeラーニング導入は、以下のような手順で実施します。
- 目的・目標の設定
- 研修内容設計
- システムの選定
- 教材の選定・作成
- 運用体制の構築
- 効果測定・改善
eラーニングシステムを選定する際は、以下の4つのポイントを比較しましょう。
- コンテンツの充実度
- 教材のカスタマイズのしやすさ
- 学習をサポートする機能
- 費用対効果
新入社員研修にオンライン研修やeラーニングを取り入れるに当たって、注意すべき点は以下の4つです。
- 受講環境の整備
- 学びを実践する場の設置
- 受講者のモチベーション維持
- 質疑応答やコミュニケーションの機会確保
新入社員研修にオンライン研修やeラーニングを取り入れた企業の事例として、以下の2社を紹介しました。
- TOPPANホールディングス株式会社(旧:凸版印刷株式会社)
- 株式会社スポーツオアシス(旧:株式会社東急スポーツオアシス)
新入社員研修のオンライン化は、コロナ禍を経てある程度定着しているといえます。企業は自社の課題やニーズに合わせて、オンライン研修と集合研修を組み合わせるなど効果的な研修プログラムを構築していくことが重要です。
新入社員研修のコスト削減や学習効果の向上に興味をお持ちの企業の方は、ぜひオンライン化を検討してみてください。
- 厚生労働省「令和5年度 能力開発基本調査 調査結果の概要」,2024年6月28日公表,P52,(閲覧日:2024年10月23日) ↩︎
- TOPPANホールディングス株式会社「凸版印刷、新入社員在宅オンライン研修の成果について」,『TOPPAN』,(閲覧日:2024年10月23日) ↩︎
参考)
日本アイ・ビー・エム株式会社「「ニューノーマルな働き方を考える」在宅ワークでの新入社員とのコミュニケーション」,『IBM』,https://www.ibm.com/blogs/think/jp-ja/newnormal-telework-communication-newemployee/(閲覧日:2024年10月23日)
TOPPANホールディングス株式会社「凸版印刷、2021年度新入社員在宅オンライン研修の成果について」,『TOPPAN』,https://www.holdings.toppan.com/ja/news/2021/07/newsrelease210730_1.html(閲覧日:2024年10月23日)
TOPPANホールディングス株式会社「凸版印刷、メタバースでの交流を取り入れた新入社員研修をフルオンラインで実施」,『TOPPAN』,https://www.holdings.toppan.com/ja/news/2022/03/newsrelease220330_1.html(閲覧日:2024年10月23日)