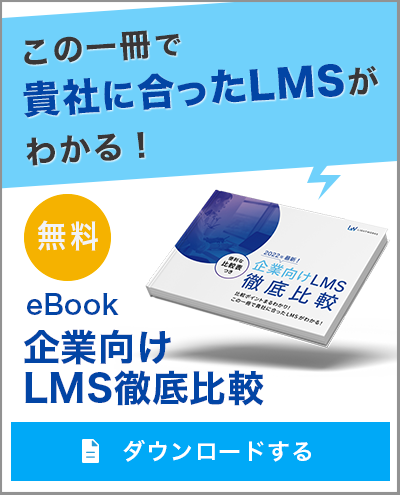【失敗&成功事例】ナレッジマネジメントを成功させるポイントを解説
最終更新日:

「せっかくナレッジマネジメントを導入したが、あまり使われていないようだ」
ナレッジマネジメントは、従業員が持つ知識やスキルを組織内で有効活用し、業績アップにつなげる経営手法です。近年その重要性が注目され、多くの企業が導入しています。しかしナレッジマネジメントを導入したものの従業員にあまり活用されていない、そもそもナレッジが集まらないというケースも見られます。
もし、自社でのナレッジマネジメントを成功させたい、もしくは導入したものの効果がイマイチなので改善したいという課題をお持ちであれば、失敗事例や成功事例からヒントを学び、自社に合った対策を行うことが有用です。
本記事では、ナレッジマネジメントの基礎知識をはじめ、陥りやすい失敗パターンを3つ紹介し原因と対策を解説します。また、ナレッジマネジメントの成功のポイントと実際の成功事例も紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
従業員のノウハウをデータ化して活用⇒ eラーニング教材制作サービスを詳しく見る
ナレッジマネジメントの基本知識
まずナレッジマネジメントの基本知識として、ナレッジマネジメントの概念と導入した際のメリット・デメリットを確認しましょう。
ナレッジマネジメントとは
ナレッジマネジメント(knowledge management)とは、従業員が持つ知識や経験、技術などを組織全体で共有し活用することで、企業の業績アップを目指す経営手法です。
“暗黙知”と呼ばれる従業員のノウハウや経験を、言語・図表などの“形式知”としてデータ化し企業内で共有することにより、業務の効率化や企業価値の創出を果たすことを目的としています。
ナレッジマネジメントは特に新しい手法ではありませんが、人材の流動化やIT技術の進歩に伴う手法の進化などにより、近年あらためて注目されています。
ナレッジマネジメントの詳しい基礎理論についてはこちら
企業におけるナレッジマネジメント導入のメリット
ナレッジマネジメントの導入により期待できる企業へのメリットは、主に以下の4つです。
生産性の向上
従業員が持つ知識やノウハウを組織で共有できれば、他の従業員がスムーズに業務を進められるようになります。その結果、業務の効率化や組織全体の生産性向上につながります。
企業競争力の強化
若手従業員や他部署の従業員がベテラン従業員のノウハウを入手できるようになるため、個人のスキルアップはもちろん、企業の競争力強化が期待できます。
業務の属人化防止
担当者しか分からない業務内容やベテランだけが持つノウハウなどを、データ化(形式知化)して管理することにより、業務の属人化を防ぐことができます。
人材教育の労力削減
組織全体で共有されたナレッジ情報を従業員が自分でいつでも入手できるため、教育担当者の人材教育の時間・労力が削減されます。
従業員のノウハウをデータ化して活用⇒ eラーニング教材制作サービスを詳しく見る
企業におけるナレッジマネジメント導入のデメリット
ナレッジマネジメントを導入する際には以下のようなデメリットもあります。導入の前には必ず確認しておきましょう。
コストと時間の負担がある
ナレッジマネジメントの導入には、ツールの費用や人件費などの初期費用やランニングコストがかかります。また、現状把握などの導入前準備やツール選定などに時間を要します。
従業員への浸透が難しい場合がある
ナレッジマネジメントの重要性を従業員全員に理解してもらうことが難しい場合があります。例えば、忙しくてナレッジ共有に時間を割けない、ノウハウを共有したくないといった従業員が出てくるケースです。従業員全員に浸透させなければ、ツールが十分に活用されないリスクがあります。
ITツール操作を習得する負担がある
ナレッジマネジメントで導入するツールやシステムを従業員が使いこなせるようになるまでには、ある程度の時間がかかります。特にITツールに不慣れな従業員にとっては、操作の習得に難しさを感じることがあります。
ナレッジの管理に手間がかかる
ナレッジマネジメントを効果的に活用するためには、ナレッジの管理が欠かせません。例えば、ナレッジを追加する際には既存データとの重複がないようにしなければなりません。蓄積された情報が古くなっていないかを定期的に確認する必要もあります。
ナレッジマネジメントのツール紹介についてはこちら
ナレッジマネジメントで起こりがちな失敗の事例と対策
ナレッジマネジメントを始める際には、多くのケースでツールやシステムが利用されます。しかしツールやシステムを導入しただけでは、組織や企業の業績アップにまでつなげることは難しく、失敗に陥ってしまう事例も少なくありません。
ナレッジマネジメント導入での失敗にはいくつかのパターンがあります。以下に陥りがちな失敗事例をまとめます。原因と対策も併せて解説しますので確認しておきましょう。
失敗パターン1:ナレッジマネジメントのツールやシステムが利用されない
【事例】ネットワーク上で営業活動情報を全社に開示し、顧客と接点が多い営業からの情報を全社で情報共有することで組織全体の生産性向上を図ったが、なかなか全社的な利用がなされていない。
【考えられる原因】ナレッジマネジメントの必要性や目的が組織全体で認識されていない
【対策】ナレッジマネジメントの目的の重要性や価値を従業員全員が理解できていない場合、積極的な情報共有が進まずプロジェクトが失敗することがあります。「組織全体の成長のため」というナレッジマネジメントの目的を組織全体に浸透させ、従業員に個々の業務と結び付けてもらうことが必要です。
この点で成功した具体例を1つ挙げてみましょう。不動産サービス業の株式会社テンポイノベーションでは、新入社員の定着率向上と、研修担当者の負担軽減という目的の下、社内に分散していた営業ナレッジを整理し300本の動画にして教材化しました。
この教材を活用した結果、新入社員の早期戦力化・定着率向上と、研修担当者の大幅な負担軽減が実現しました。組織にとって重要な目的を果たすため、関係者全員がナレッジマネジメントの必要性や価値を理解しているからこそ効果が生まれている事例です。
株式会社テンポイノベーションの詳しい事例紹介はこちら
失敗パターン2 :ナレッジは集まったが、必要な情報を効率的に探せない
【事例】新入社員の早期育成や知識共有のために、社内で蓄えた情報を再利用するナレッジ共有を行った。しかしナレッジであるドキュメントの情報が体系的に保管されておらず、必要な人が求める情報を効率的に検索できない。更新済みの情報なのかもわからない。その結果、検索時には1つずつ内容を確認する手間が発生した。
【考えられる原因】ツールやシステムの運用ルールが欠けている
【対策】システムを導入しても運用ルールが整備されていない場合、ナレッジが未分類・未整理の状態で蓄積されてしまいます。その結果、データが乱雑化し必要な情報を得ることができず、システムやツールの効率的な活用に至りません。
情報提供者と情報利用者の両方に対する運用ルールやマニュアルなどの整備が必要です。またナレッジマネジメントリーダーによる勉強会などを行い、周知・教育を地道に促進していくことも不可欠です。
失敗パターン3:ナレッジ共有の習慣が続かない
【事例】導入当初はナレッジが順調に蓄積されていたが、従業員たちの通常業務が忙しく、次第にナレッジの蓄積や更新が行われなくなってしまった。また、ベテラン従業員は独自にノウハウを蓄積していて、システム上に登録しない。
【考えられる原因】従業員がナレッジ共有のメリットを感じられないため、自発的なナレッジ共有が進まず習慣化されない
【対策】従業員がナレッジを共有するメリットを感じていないと、ナレッジマネジメントのツールやシステムを使わなくなる可能性があります。
ナレッジを共有する行動に対し、「褒賞などのインセンティブを設ける」「人事評価制度に反映させる」などの施策を検討しましょう。継続のモチベーションに結び付くような仕組みを繰り返し計画することが重要です。
ナレッジマネジメントを成功に導く導入時のポイント
ナレッジマネジメントの失敗を避ける対策を学んだ後は、ナレッジマネジメントの成功に欠かせない導入時のポイントをまとめます。
導入後のゴールを明確にしておく
ナレッジマネジメントをスタートさせる際は、「組織全体の成長のため」「経営ビジョンの実現のため」といったナレッジマネジメント導入の目的を従業員全体に浸透させることが不可欠です。
その上で、ナレッジマネジメントで成し遂げたいゴールを明確化し、従業員で共有することが重要です。明確にしておきたいゴール内容を以下にまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。
明確にしておきたいゴール内容
□何のために知識を共有するのか
□誰の知識を共有したいのか
□どのような知識を共有したいのか
□その結果、どのような状態になっていたいのか
□そのために運営側は何を行うのか
引用元:佐別当隆志, 小谷美佳「エンタープライズソーシャルネットワークを活用したナレッジマネジメント」,『情報の科学と技術』,Vol.62,No.7,2012,p.301.
ナレッジマネジメント専任のチームやリーダーを決めておく
ナレッジマネジメントという取り組みを従業員に定着させるためには、ナレッジを共有しやすい環境が整っていなければなりません。
その環境作りに不可欠なのがナレッジマネジメント専任のチームやリーダーです。専任チームやリーダーは、ツール利用やナレッジ共有を促進する声掛けや勉強会などを担当し、ナレッジマネジメントが組織全体に定着するように率いる能力が求められます。
スモールスタートを徹底し、効果を測定できるようにしておく
ナレッジマネジメントを導入しても、最初から全従業員による協力や継続的な参加を得ることは難しいでしょう。まずは効果を上げやすい部署だけで、対象ナレッジの範囲を絞るなどしてスモールスタートで成功体験を重ねた後に、徐々に拡大していくことが成功への近道です。
スタートの際には、業績向上に関連する活動前の状況等を定量的な数値で取得しておくとよいでしょう。ナレッジマネジメント導入後の効果を把握することが可能になり、その後の展開や継続を促します。
従業員のノウハウをデータ化して活用⇒ eラーニング教材制作サービスを詳しく見る
ナレッジマネジメントの成功事例
最後に、実際に企業で行われたナレッジマネジメントの成功事例を2つ紹介します。
成功事例1:日立GEニュークリア・エナジー株式会社
原子力サービスを行う日立GEニュークリア・エナジー株式会社では、ベテラン世代の知識や技術を組織的に管理し、次世代に継承していくことが重要な課題となっていました。
そこで、社内調査で社内業務改革の技術伝承に関わる課題を明確化し、ナレッジマネジメントの導入を進めました。
この取り組みでは、ナレッジマップを作成して技術領域ごとに保有する知識を洗い出し、技術伝承の優先度を可視化しました。これによりナレッジを体系的に管理することができるようになったといいます。
また、ナレッジマネジメント活動を活性化するために「ワールドカフェ(話しやすい雰囲気で行われる対話集会)」や「ナレッジ連絡会(技術伝承活動の課題等の共有)」を開催するなどのプロモーションを行い、従業員間のナレッジ共有を促進しました。
同社は、ナレッジマネジメント成功の鍵として以下の3点を挙げています。
- 経営課題とナレッジマネジメント戦略をリンクさせること
- ナレッジマネジメントの推進ガバナンスを構築すること
- 活動ロードマップを定め段階的に推進すること
成功事例2:オムロン株式会社ファクトリーオートメーション事業
オムロン株式会社のファクトリーオートメーション事業は、顧客の製造現場での課題に向けた技術ソリューションをグローバルに提供しています。同事業では、個々のエンジニアや各担当拠点に留まっていた技術ナレッジをグローバルに共有・活用するナレッジマネジメントシステムを構築しました。
蓄積する技術ナレッジは、技術開発、実証実験、操作マニュアルなどエンジニアの活動成果物とすることにより、ナレッジ文書作成の作業負担を軽減し、ナレッジの蓄積件数の増加につなげることができました。
また、同社の標準ITインフラであるMicrosoft Office365とSharePoint Onlineを利用して情報システムを構築し、技術ナレッジの管理と共有を効率化しました。
グローバルな共有システムにおいては、利用者が輸出管理などの技術の取り扱いを気にすることなく、参照可能な範囲における技術ナレッジを自由に活用できる利便性を実現しました。
こうしたナレッジマネジメントの結果、二重開発を防ぎ拠点間のアクセスが促進され、顧客へのソリューション提供の質と効率を向上させています。
ナレッジ蓄積が成功した理由として、同社は以下の点を挙げています。
- 技術ナレッジがエンジニアの通常業務の成果を文書化するものであったため、エンジニアにとって過度な負担なくナレッジ共有できた
- 文書化する技術ナレッジを体系化しそれをガイドとして示したことにより、技術ナレッジの文書化が促進された
- 技術ナレッジを各拠点により管理する方法を取ったことで、各拠点の自発的な蓄積が促進された
以上、ナレッジマネジメントの成功事例を2つ紹介しました。どの事例もナレッジマネジメントの目的が明確で、ナレッジ情報を効率的に蓄積・活用できており、事業の成果につなげていることが分かります。ぜひ参考にしてください。
従業員のノウハウをデータ化して活用⇒ eラーニング教材制作サービスを詳しく見る
まとめ
ナレッジマネジメントとは、従業員が持つ知識や経験、技術などを組織全体で共有し活用することで、企業の業績アップを目指す経営手法です。
ナレッジマネジメントでは、従業員の“暗黙知”と呼ばれるノウハウや経験を、言語・図表などにデータ化し、企業内で共有・蓄積されたナレッジを管理します。
ナレッジマネジメントの導入により期待できる企業へのメリットは、主に以下の4つです。
- 生産性の向上
- 企業競争力の強化
- 業務の属人化防止
- 人材教育の労力削減
導入する際には以下のようなデメリットもあります。
- コストと時間の負担がある
- 従業員への浸透が難しい
- ツール操作を習得する負担がある
- ナレッジの管理に手間がかかる
ナレッジマネジメントで起こりがちな失敗パターンを3つ解説しました。
失敗パターン1:ナレッジマネジメントのツールやシステムが利用されない
失敗パターン2:ナレッジは集まったが、必要な情報を効率的に探せない
失敗パターン3:習慣が続かない。継続的に利用されずシステムが陳腐化
ナレッジマネジメントを成功に導く導入時のポイントは以下の通りです。
- 導入後のゴールを明確にしておく
- 専任のチームやリーダーを決めておく
- スモールスタートを徹底し、効果を測定できるようにしておく
最後にナレッジマネジメントの成功事例を2つ紹介しました。
- 日立GEニュークリア・エナジー株式会社
- オムロン株式会社ファクトリーオートメーション事業
ナレッジマネジメントの他社事例を学ぶことで、成功のこつや失敗パターンを確認でき、自社に合った対策を見い出すことも可能になります。ぜひ本記事を参考にして成果につながるナレッジマネジメントを目指しましょう。
参考)
社団法人日本情報システム・ユーザー協会「平成12年度・ナレッジマネジメント研究部会 報告書 経営を変革するナレッジマネジメント~その研究と提言~」,https://www.juas.or.jp/cms/media/2017/01/00knowledgemngmt.pdf(閲覧日:2024年11月27日)
社団法人日本情報システム・ユーザー協会「平成14年度 ナレッジマネジメント研究部会 報告書 日本企業に最適なナレッジマネジメントの実践的活用の研究」,https://www.juas.or.jp/cms/media/2017/01/02knowledgemngmt.pdf(閲覧日:2024年11月27日)江部ゆり夏,島田剛志「ナレッジマネジメント2.0で実現する企業力向上」, 『知的資産創造』, 2022年7月号,p.72-85.
社団法人日本情報システム・ユーザー協会「平成13年度ナレッジマネジメント研究部会報告書 経営に役立つナレッジマネジメントの活用」,https://www.juas.or.jp/cms/media/2017/01/01knowledgemngmt.pdf(閲覧日:2024年11月27日)
八木理 他「次世代に技術をつなぐ原子力分野でのナレッジマネジメント活動」,『日立評論』, Vol.102,No.2,2020,p.136-140.
赤松康至「技術ナレッジのグローバル共有化の仕組み構築と活用」,『OMRON TECHNICS』, Vol.55,No.1,2023,p.108-114.