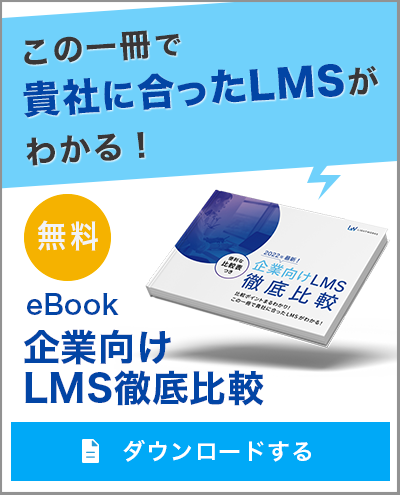MR教育とは?導入・継続教育の基本や効果を高めるポイント、事例を解説
最終更新日:

「MR教育制度の新制度への対応として、自社で行う研修も見直していきたい」
MR認定試験やMR認定証交付について定めている「MR認定要綱」の改定案が公表され、2026年度から新制度への移行が予定されています[1]。
新制度では、MRの教育制度の枠組みが大きく変更されます。従業員個人の学びが鍵となる新制度において、個々がMRの資格を維持し、継続的に活躍していくためには、企業は今まで以上に従業員の自律的な学びを支援していかなくてはなりません。
そのためには、MR教育効果の向上や、MR教育担当者のスキルアップのポイントを知っておく必要があります。
この記事では、MR認定制度の概要や教育の効果を高めるポイント、新制度の変更点などを分かりやすく解説します。最後に特徴的な教育を行う企業事例も紹介しますので、MR教育の充実や新制度移行の備えとしてお役立ていただければ幸いです。
人材育成計画の方法から効果的な教育手法までこれ1冊で解説! ⇒ 「人材育成大百科」を無料ダウンロードする
目次
MRの定義とその役割
MRとは英語の「Medical Representative(メディカル・リプレゼンタティブ)」の略で、医薬情報担当者を意味します。
MRは製薬企業に所属、またはCSO(Contract Sales Organization:医薬品販売業務受託機関)から製薬企業に派遣され、自社医薬品の情報提供活動を行います。
まずは、MRの定義と役割について確認しましょう。
MRの定義
公益財団法人 MR認定センターの「MR認定要綱」によると、MRについて以下のように定義されています。
この要綱で「MR」とは、企業を代表し、医薬品の適正使用並びに薬物療法の向上に貢献するために、医療関係者と面談又は電子ツール等を用いた情報交流を通じて、医薬品の品質・有効性・安全性等に関する情報の提供・収集・伝達を主な業務として行う者をいう。
引用元:公益財団法人 MR認定センター「MR認定要綱」,2021年4月1日公表,p1(閲覧日:2024年9月25日)
もう少し簡単に説明すると、MRは自社製品の正しい使用法や品質、有効性、安全性といった情報を医師や看護師、薬剤師などの医療関係者に提供する情報提供担当者です。自社の医薬品を医療機関に採用してもらうほか、副作用情報の収集や、医薬品のフィードバックをもらって自社の開発部門に伝えることなどが主な業務です。
MRは一般的な営業職とは異なり、医療機関に直接医薬品を販売せず、情報提供のみを行います。医療機関への販売や価格交渉は、医薬品卸売業者の営業である「MS(Marketing Specialist:医薬品卸販売担当者)」が行います。
MR認定制度とは?
「MR認定制度」とは、必要な基礎教育(導入教育)を修了してMR認定試験に合格し、6カ月のMR経験を持つ人にMR認定証を発行する制度です。
MR認定証の有効期限は5年で、更新するには所定の教育(継続教育)を修了する必要があります。 MR認定証がなければMRの業務ができないというわけではありません。しかし、製薬会社やCSO(医薬品販売業務受託機関)の多くは、自社MRに取得を義務付けています。
MR認定制度を運用するMR認定センターは、「MRが高い倫理観を持ち、患者の立場から医薬品の適正使用情報を提供・収集することで医療や社会に貢献する」という理念と、この理念を通じて「医療関係者から信頼されるパートナーを目指す」という将来ビジョンを掲げています。
MRに必要な教育
MRに必要な教育は、大きく以下の2つに分類されます。
- MR認定試験の合格・MR認定証の取得を目指す従業員が受ける「導入教育」
- MR認定証の取得後に受ける「継続教育」
ここでは、それぞれの主な内容を解説します。
新入社員が受ける「導入教育」とは?
導入教育とは、知識や技能、倫理観など、MRに必要な最低限の資質を習得するための研修です。「基礎教育」と「実務教育」の2つがあります。
「基礎教育」では、テキスト教材を使って「医薬品情報」「疾病と治療」「MR総論」の3科目を学びます。
「実務教育」では、MRの実践的な資質習得のために、以下の7つの科目について学びます。
- 倫理教育
- 安全管理教育
- 技能教育
- 実地教育
- 製品教育
- 製品関連知識
- その他教育
このうち、倫理教育、安全管理教育、技能教育は、各企業が、企業理念に基づいて導入教育の実施ごとに「GIO(一般目標)」と「SBO(到達目標)」を定め、教育研修と成果確認を行います。
基礎教育と実務教育にかかる期間は企業によって異なりますが、それぞれ2カ月ほどです。MR認定センターの教育研修システム認定を受けた企業(登録企業といいます)に在籍している人は、両方の研修を社内で受講できます。
登録企業に在籍していない場合、基礎教育はMR認定センターが指定するMR導入教育実施機関で受けられます。しかし、MR導入教育実施機関では実務教育は受けられないため、登録企業に入社して受講する必要があります。
なお、MR認定証取得までの道のりは以下のようになっています。
(1)導入教育の「基礎教育」受講・修了認定
(2)MR認定試験に合格
(3)所属企業で導入教育の「実務教育」受講・修了認定
(4)6カ月のMR経験
(2)~(4)がそろうと、MR認定証が交付されます。
MR認定証取得後の「継続教育」とは?
前述の通り、MR認定証の有効期限は5年間であるため、更新するには「継続教育」を受ける必要があります。
継続教育も、「基礎教育」と「実務教育」の2つで構成されています。
「基礎教育」では、MR学習ポータルに搭載されている基礎教育年次ドリルを所定の期限までに全問正解することで、修了認定を受けられます。個人で毎年受講し、完了する必要があります。
「実務教育」では、導入教育と同様の7科目を、企業側が継続的・計画的に実施します。
7科目のうち倫理教育、安全管理教育、技能教育については、企業理念に基づき、各企業が導入教育の実施ごとに「GIO(一般目標)」と「SBO(到達目標)」を定め、教育研修と成果確認を行います。
導入教育と同様、継続教育の「実務教育」も登録企業でしか実施できません。自社のMRにはどのような研修が必要か、教育コンテンツは内製か委託か、実施方法は集合研修かeラーニングかなどをよく検討して実施する必要があります。
MRは情報提供活動で多忙なため、例えば、時間や場所を選ばずに学習を進められるeラーニングは、集合研修よりも利便性が高いでしょう。
ベンダーによっては、社内資料のPPTや研修動画をeラーニング化するなど、自社のニーズに合わせて比較的手軽にコンテンツを作成できる場合もあります。気になるサービスがあれば、ぜひ問い合わせをしてみましょう。
制作実績21年以上!学習効果の高い教材作成 ⇒ ライトワークスのeラーニング教材制作サービスを詳しく見る
MR認定制度は2026年度から新制度に移行
2章までで紹介したMR認定制度は、「MR認定要綱」改定のため、2026年度から新制度への移行が予定されています。
新制度では、教育体系が大きく変更されます。現行の「導入教育」と「継続教育」の区分は撤廃され、個人が行う「基礎教育」と、企業が行う「実務教育」の、シンプルな2階建て方式となります。
基礎教育の科目は、現行の「医薬品情報」「疾病と治療」「MR総論」のうち、「MR総論」が「医薬品産業と倫理・法規・制度」に変更されます。企業が将来的にMR以外の職種にも試験を活用できるよう、MRに特化せず、医薬品産業従事者が共通して理解すべき内容とされます。
また、MR認定制度の見直しも行われます。MR認定試験の名称を「MR基礎試験」と改めるほか、以下の点が変更となります。
- 受験資格の撤廃
- 受験機会や受験会場の増加
- 認定証の交付要件である「MR経験6カ月」の廃止 など
合格証や認定証は、所定の個人学習を毎年行うことで、5年ごとに更新が可能です。
要綱改定の背景には、デジタル化や新薬開発の高度化・専門化といった、ビジネス環境の急激な変化があります。
現状、MR教育は企業主導で行われていますが、新制度では、MR自身が人命に関わる医薬品の情報を扱う自覚と責任を持ち、主体的に学習を進める必要があります。企業は、優秀なMRの確保・維持のため、自社MRに自律的な学びを促す仕組みを構築することが重要です。
自社MRの学習支援・管理はLMSが便利 ⇒ 製薬企業におけるLMS(学習管理システム)CAREERSHIPの導入イメージを詳しく見る
MR教育の効果を高めるポイント
新制度への移行を控え、MR教育の重要性はますます高まっています。ここでは、教育の効果を高める5つのポイントを紹介します。
動画教材を積極的に活用する
動画教材は、テキスト教材と比べて視覚効果が高く、記憶に残りやすいのがメリットです。また、講師によって内容にむらが出ることがなく、会場費や講師料などのコストも削減できます。
MRにとって動画教材は、座学で得た知識を情報提供活動でどのように生かすかを学ぶのに最適です。例えば、ロールプレイング研修の様子を撮影し動画教材を作成すれば、お手本として繰り返し学習できます。
COP[2](倫理的な指針)や公正競争規約[3](景品類に関するルール)違反の事例学習も、動画での学びは気を付けるべきポイントがより分かりやすくなります。
動画教材の活用が、従業員の早期育成や社内に分散したナレッジの整理など、今抱えている教育課題を解決するケースもあります。自社のニーズを踏まえた動画教材に関心のある方は、ぜひ以下の当社事例をご覧ください。
アウトプットの時間を多く確保する
インプットした知識を生かすには、アウトプットの訓練が必要です。アウトプットの時間をなるべく多く確保しましょう。
例えば、インプットは研修前に各自eラーニングなどで行い、集合研修では重要なポイントの確認や、知識が身に付いているかのテストをする程度にとどめれば、アウトプットに多くの時間が使えます。このように2種類の学習方法を組み合わせるやり方を、ブレンディッド・ラーニングといいます。
また、アウトプットの質によって、従業員がMRに求められるスキルや資質等をクリアしているかどうかを把握し、人事評価にも活用できます。
関連 ▶ ブレンディッド・ラーニングとは 研修とeラーニングのうまい組合せ方(弊社コンプライアンス情報サイトへ移動します)
現場のニーズを把握する
現場のニーズを把握し、それに応える研修を行いましょう。実施する研修が、現場のどのような問題を解決するのかが、明確であることが重要です。
例えば、プレゼン研修を行う理由が、「一般的に情報提供活動で重要とされているから」というだけでは、高い効果は期待できないでしょう。
しかし、自社のMRに「医師となかなか面会できない」「面会ができても、処方アップにつながりにくい」という傾向が見えたため、これを解決するためプレゼン研修を行う、と周知すれば、受講者の目的意識も高くなり、効果が出やすいといえます。
体験談を整理・共有する
新制度への移行を控え、MRの主体的な学びが重要性を増す中、体験談の共有は効果的です。
困難な状況を、どういった方法で乗り切ったかという成功例はもちろん、失敗談も貴重な研修材料になります。
「なぜ失敗したか」「どうすれば成功できたか」などを分析、整理して誰でも確認できる仕組みやシステムを構築・導入するとよいでしょう。
ナレッジマネジメントを工夫する
現場の管理職とMR教育担当者の連携を強化し、効果の高いナレッジマネジメントを行いましょう。
プレイヤーとしての経験・実績が豊富な管理職でも、部下の指導には慣れていないケースは少なくありません。この場合、管理職自身の成功体験を基に、指導する事項を整理するとよいでしょう。
MRはその各項目について、自身がクリアできているかどうかを確認し、課題発見や目標設定に生かします。このような情報をMR教育担当者と共有すれば、両者の連携で効果的な研修の実施が可能です。
MRの自律的な学びは大変重要ですが、全てをMRに委ねるのではなく、方向性を示すことは大切です。現場上司とMR教育担当者の連携によって研修の目的や期待する効果を明確にすれば、優秀なMRを育成できるでしょう。
関連 ▶ ナレッジマネジメントで業務効率化!成功のポイント、事例も解説
MR教育担当者の育成も重要に
医学、ITなどの進歩に伴い、MRに求められる知識や情報量は急増しています。身に付けた知識や情報の使い方も高度化・複雑化しており、研修では従来の講義中心のスタイルから、問題解決を学ぶ実践中心のスタイルが求められるようになっています。
そのため今日では、教育担当者の資質や指導力の向上も重要になっているのです。
MR教育担当者の資質向上については、それを目的とした学習ポータルを設計・開発した研究者たちによる研究結果[4]が公表されています。
この研究結果によると、教育担当者の自発的な学びを促進する教育プログラム作成のための着眼点として以下の5つが見いだされ、妥当性が確認されています。教育プログラムの作成時に意識してみるとよいでしょう。
- ユーザー第一主義である
- 業務に役立つコンテンツが充実している
- 学習者同士のコミュニケーションツールが設置されている
- 4「省察」の場となるよう問いかけを行う(内省とコーチングができる)
- MR教育者としてのあるべき姿(ゴール)を示す
また、MR認定センターの「2024年版 MR白書」[5]によると、企業の教育研修専従者一人あたりが受け持つMRの数は、50人未満(72/199社)、100人未満(33/199社)が多い結果となっています。企業は、スパン・オブ・コントロール、すなわち担当者一人がコントロール可能な人数や業務の領域を見直す必要があるとされています。
この調査では、「教育研修専従者が不在」という回答も、50/199社と多くありました。こうした企業では、兼務者からのバックアップ体制の確保や、次の担当者へのスムーズな引き継ぎが行える仕組みづくりにより、MR教育を円滑に実施することが求められます。
MR教育の事例
最後に、特徴的な独自のMR教育を実施している企業の事例を紹介します。ぜひ自社の教育プログラム設計の参考としてください。
住友ファーマ株式会社
住友グループの製薬会社である住友ファーマ株式会社では、新入社員がMRの基礎を3年かけて学ぶ「ベーシック研修」プログラムを実施し、医療従事者の課題を解決できる人材育成に取り組んでいます。
入社後の導入研修ののち、先輩MRの1on1によるサポートを受けながらMRの基本を半年間かけて学びます。その後、2~3年目には「DEGEICO」研修で、さらにMRとしての知識や理解を深めていきます。
住友ファーマ株式会社独自の研修である「DEGEICO」は、所属営業所以外の優秀な先輩MRを「師匠」とし、「弟子入り」する制度です。半年間を1クールとし、2年間で2~4クールの研修を実施します。
優秀な先輩MRの活動を見て学ぶだけでなく、定期的な面談により一人一人のMRスタイルの早期確立を目指します。「DEGEICO」を通した研修は、スキルはもちろん、MRとしての意識向上にも寄与し、成長を促します。
大鵬薬品工業株式会社
大塚ホールディングス傘下の大鵬薬品工業株式会社では、「人財」育成として、専門的な知識や技能だけでなく、情報収集や分析をしたり、思いやりの気持ちを持ち、自ら考えて行動したりできる「人間力」を養う研修を、継続的に実施しています。
同社では、新型コロナウイルスの感染拡大をきっかけとしたプロモーション環境の変化や、2024年以降の「医師の働き方改革」(労務管理の徹底や労働時間の短縮で、医師の健康を確保するための取り組みと支援)施行に対応すべく、「領域別MR制」への移行を計画中です。
「領域別MR制」とは、例えば、「呼吸器がん領域」「消化器がん領域」「その他特定がん領域」など、一定の領域に関する高度な知識を持ったMRが医療関係者を訪問する制度です。領域を限定することで個々の専門性を発揮しやすくし、医療関係者のニーズを満たします。
領域専門MR育成のためのプログラムとして、集合研修(オンライン研修)や「振り返り研修」「ワークショップ」「論文抄読会」等による基礎/最新知識の習得をはじめ、定期的な外部アセスメントによる学習深達度の評価、選抜者に対する外部プログラムや国内外の医学薬学関連学会への参加機会の提供などがあります。
人材育成計画の方法から効果的な教育手法までこれ1冊で解説! ⇒ 「人材育成大百科」を無料ダウンロードする
まとめ
MRとは「Medical Representative(メディカル・リプレゼンタティブ)」の略で、製薬会社などの医薬情報担当者を指します。MRは製薬企業の代表として、自社の医薬品に関する正しい情報を医療関係者に伝える重要な役割を持ちます。
MRに必要な教育は、以下の2つがあります。
- MR認定試験の合格・MR認定証の取得を目指す従業員が受ける「導入教育」(基礎教育・実務教育)
- MR認定証取得後に受ける「継続教育」(基礎教育・実務教育)
製薬企業などに所属する大抵のMRが、「MR認定証」の取得を目指します。MR認定証は、必要な基礎教育(導入教育)を修了してMR認定試験に合格し、6カ月のMR経験を持つ人に発行されます(「MR認定制度」)。MR認定証の有効期限は5年で、更新するには所定の教育(継続教育)を修了する必要があります。
このMR認定制度は、「MR認定要綱」改定のため、2026年度から新制度に移行予定です。
新制度では、教育体系が大きく変更されます。現行の「導入教育」と「継続教育」の区分が撤廃され、個人が行う「基礎教育」と、企業が行う「実務教育」の、シンプルな2階建て方式となります。
また、MR認定試験についても、「MR基礎試験」への名称変更、受験資格の撤廃、MR認定証の交付要件である「MR経験6カ月」の廃止などの変更が予定されています。
MR教育の効果をより高めるポイントとして、以下の5つがあります。
- 動画教材を積極的に活用する
- アウトプットの時間を多く確保する
- 現場のニーズを把握する
- 体験談を整理・共有する
- ナレッジマネジメントを工夫する
MR教育担当者の教育プログラムを作成するポイントとして、以下の5つがあります。
- ユーザー第一主義である
- 業務に役立つコンテンツが充実している
- 学習者同士のコミュニケーションツールが設置されている
- 「省察」の場となるよう問いかけを行う(内省とコーチングができる)
- MR教育者としてのあるべき姿(ゴール)を示す
最後に、独自のMR教育を行う企業の事例を紹介しました。
- 住友ファーマ株式会社
- 大鵬薬品工業株式会社
2026年度に施行予定の新制度においては、さらにMRの自律的な学びが重要になります。MR教育の効果を高めるポイントを押さえ、教育担当者の資質向上に向けた取り組みも実施しながら、MR教育を充実させていきましょう。
[1]公益財団法人 MR 認定センター「MR 認定制度改革有識者会議 検討結果報告書」,P15図3,2024年2月公表, (閲覧日:2024年10月10日)
[2] 日本製薬工業協会「製薬協コード・オブ・プラクティス」,2013年1月公表, (閲覧日:2024年10月10日)
[3] 医療用医薬品製造販売業公正取引協議会「公正競争規約」,(閲覧日:2024年10月10日)
[4] 森田晃子,根本淳子,江川良裕,鈴木克明「MR教育者の自主的な学習を促す学習ポータルの開発」,『日本教育工学会論文誌』, 34巻, Suppl.号, 2010, p161-162.
[5] 公益財団法人 MR認定センター「2024年版 MR白書」,2021年7月公表, (閲覧日:2024年9月26日)
参考)
公益財団法人MR認定センター「MR認定制度の紹介」,https://www.mre.or.jp/whatsmr/ninteioutline/(閲覧日:2024年9月25日)
公益財団法人MR認定センター「MR認定証取得までの道のり」,https://www.mre.or.jp/ninteiexam/roadmap/(閲覧日:2024年9月25日)
公益財団法人MR認定センター「MRになるためには」,https://www.mre.or.jp/whatsmr/workasmr/(閲覧日:2024年9月25日)
株式会社エリメントHRC「未経験者必見!MR研修の目的と内容を徹底解説」,『医療転職.com』,https://www.iryo-tenshoku.com/column/detail.html&id=78(閲覧日:2024年9月25日)
公益財団法人MR認定センター「MRの継続教育について」,https://www.mre.or.jp/holder/education/(閲覧日:2024年9月25日)
株式会社クイック「MR教育『個人の主体的な学習』に重点…26年度から新制度、認定試験大幅見直し」,『AnswersNews』,https://answers.ten-navi.com/pharmanews/28620/(閲覧日:2024年9月25日)
サンライトヒューマンTDMC株式会社「自ら考え、成果をあげる人材を育てるために教育担当者に求められること。~MR教育編~」,https://www.slhtdmc.co.jp/labo/bid/interview2017/(閲覧日:2024年9月26日)
株式会社デジタル・ナレッジ「社内研修に動画を用いるメリットは?」,https://www.digital-knowledge.co.jp/solution/training/videos/(閲覧日:2024年9月26日)
住友ファーマ株式会社「『自律・挑戦・突破』プロフェッショナルMRを育成する」,https://www.recruit.sumitomo-pharma.co.jp/gradu/effort/mr_training/(閲覧日:2024年9月27日)
大鵬薬品工業株式会社「『人財』育成」,https://www.taiho.co.jp/recruit/training/(閲覧日:2024年9月27日)