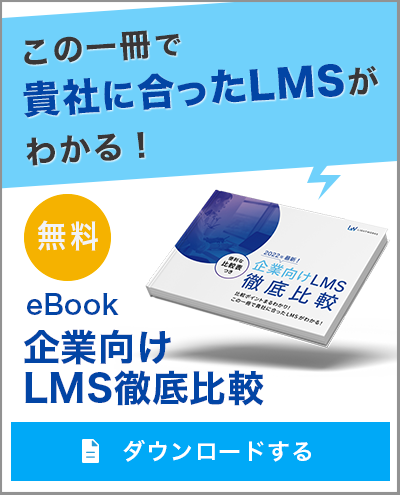パートナー教育とは?効果的な進め方や実践ポイント、企業事例を解説
最終更新日:

「パートナー教育で、現場全体のパフォーマンスをアップしたい」
昨今は多くの企業で人材不足が深刻化しており、採用とともに既存従業員の教育に注力しています。特に製造業・建設業など、パートナー企業(協力会社)とビジネスを展開する企業は、パートナー企業の従業員にも教育を行う必要があります。
例えば建設業界では、パートナー企業(協力会社)の幹部・一般従業員を対象とした安全管理研修会の実施、次世代の職人育成、スキルアップ支援などの取り組みが実際に行われています。
適切なパートナー教育によって、自社の現場における労働災害や情報セキュリティ事故を防げる他、自社とパートナー企業(協力会社)の競争力強化や生産性向上も可能になります。
この記事では、パートナー教育の重要性やメリット、効果的な教育方法、パートナー企業(協力会社)に向けた教育を行う企業事例などをご紹介します。自社の将来を担う人材育成の参考になれば幸いです。
人材育成計画の方法から効果的な教育手法までこれ1冊で解説! ⇒ 「人材育成大百科」を無料ダウンロードする
目次
なぜパートナー教育が必要なのか?
パートナー教育は、企業競争力を高める上で自社の従業員への教育と同じくらい重要です。まずは、パートナー教育の重要性について確認しましょう。
そもそもパートナー企業(協力会社)とは?
パートナー企業とは、自社と共同でビジネスを行う企業のことです。特に建設業界におけるパートナー企業は「協力会社」と表現され、工事の委託先を指します。
パートナー企業(協力会社)と事業を行う企業は、建設、製造、IT、広告など幅広い業界に存在します。
パートナー企業(協力会社)と協力する目的は、互いが持つ知識や技術、人材などの強みを生かして共通の目標を達成したり、単独では得られない大きな成果を上げたりすることです。なお、パートナー企業(協力会社)同士は対等な立場であり、上下関係はありません。
パートナー企業(協力会社)から受ける影響は、事業規模や委託する業務が拡大するにつれて高まります。自社と一心同体ともいえるパートナー企業(協力会社)の従業員には、リスク管理やスキルアップのための教育が欠かせません。
パートナー教育の重要性
建設や製造業は労働災害から従業員を守るため、安全衛生教育や「労働災害ゼロ」に向けた取り組みに積極的です。しかし、パートナー企業(協力会社)がこうした取り組みへの知識や意識を持っていなければ、現場で働く従業員の安全と健康の確保が難しくなります。
そのため、パートナー企業(協力会社)の従業員にも講習や研修などにより安全衛生教育を受けてもらうことは、安全な業務遂行のために大変重要です。
また昨今、情報セキュリティ教育も不可欠です。建設業の場合、図面など重要書類の紛失やパソコンの盗難、SNSへの現場写真の投稿など、内部関係者の過失が引き起こす情報セキュリティ事故が実際に起こっています。
このような事態を招かないよう、パートナー企業(協力会社)も含めた情報セキュリティ事故防止対策が求められています。
自社の現場に1人でも情報セキュリティに関する意識の低い人材がいると、情報漏えいのリスクが高まります。パートナー企業(協力会社)の経営者は、情報セキュリティ教育を従業員全員が受ける重要性を伝える必要があります。
また、事業規模やパートナー企業(協力会社)の役割が大きくなるほど、パートナー企業(協力会社)の従業員が持つ知識・スキルが自社の顧客獲得や売り上げに影響します。そのため、自社の従業員と同程度の教育が必要です。
ただし、自社とパートナー企業(協力会社)に上下関係はなく、関係性は対等です。パートナー教育を行う際は、相手企業の負担が大きくなり過ぎないよう配慮しながら進めましょう。
パートナー教育の目的
パートナー教育の主な目的は、以下の通りです。
労働災害の防止
建設業や製造業では従業員一人一人の健康を守るため、安全衛生教育が極めて大切です。
また、パートナー企業(協力会社)の現場は、自社の目が届きにくいため、安全衛生に関する法令や自社の作業ルールなどを学ぶ、コンプライアンス教育を行き渡らせることも、労働災害防止のために重要です。
情報セキュリティ事故の防止
パートナー企業(協力会社)とは、自社のノウハウや顧客・従業員の個人情報といった機密情報を共有する場合があります。それらが外部に漏れる情報セキュリティ事故は、自社やパートナー企業(協力会社)だけでなく、顧客や取引先、株主などにも被害が及ぶ可能性があるため、万全の対策が必要です。
日本建設業連合会などが公表している「協力会社における情報セキュリティ対策について」では、パートナー企業(協力会社)への情報セキュリティ教育に以下の内容を含めることを推奨しています。
・自社の情報セキュリティ方針の概要
・作業所での情報セキュリティの必要性
・請負業務ごとのルール、手順の確認
・情報セキュリティ事故の対応方法と再発防止策
・必須事項及び禁止事項の確認引用元:一般社団法人 日本建設業連合会・建築生産委員会 ICT推進部会・情報セキュリティ専門部会「協力会社における情報セキュリティ対策について」,2010年6月公表,p8(閲覧日:2024年12月26日)
また、情報セキュリティ事故を起こさないための教育に加え、万一、情報漏えいなどの事故が起こった場合の対応も学んでおく必要があります。
情報セキュリティ対策と事故時の対応を学ぶeラーニング ⇒ 詳しく見る
知識・スキル習得によるパフォーマンス向上
パートナー企業(協力会社)従業員へのスキルアップ支援によって、パフォーマンス向上が可能です。現場全体がレベルアップし、早期の目標達成や生産性・業績アップも期待できます。
パートナー企業の成長、事業拡大支援
パートナー教育により、パートナー企業(協力会社)の成長と事業拡大を支援できます。
パートナー企業(協力会社)の従業員が、より高度な専門性を身に付け企業として成長すれば、自社のビジネス拡大にもつながります。自社だけでは実現できない高度なサービスの提供が可能となり、競争優位性を確立できるでしょう。
長期的な関係構築とロイヤリティ向上
パートナー企業(協力会社)の成長や事業拡大を支援する過程で、自社とパートナー企業(協力会社)の間には強固な信頼関係が生まれます。
パートナー企業(協力会社)従業員の自社に対するロイヤリティ(Loyalty:忠誠心)が向上すれば、より多くの優秀な人材を長期的に確保できます。
パートナー教育のメリット
パートナー教育は、自社とパートナー企業(協力会社)の双方に良い影響をもたらします。ここでは、パートナー教育がもたらす具体的なメリットをご紹介します。
パートナー教育を行う企業側のメリット
パートナー教育を行う企業側に期待できるメリットは、以下の4点です。
売り上げアップや生産性向上
パートナー企業(協力会社)が自社のノウハウや、より高いレベルの知識・技術を得れば、商品・サービスの質や作業スピードの向上につながります。高品質な商品・サービスの提供によって顧客が増加し、売り上げアップが期待できるでしょう。
また、パートナー企業(協力会社)が、担当業務を効率的にこなせるようになり、業務効率化による生産性向上も見込めます。
ブランド価値向上
パートナー企業(協力会社)の従業員がスキルアップすることで、より質の高い商品・サービスの提供が可能になります。それによって、自社とパートナー企業(協力会社)双方のブランド価値向上につながります。
反対に、教育不足からパートナー企業(協力会社)の過失による事故などが発生すれば、自社のブランドイメージをも損なう原因となるでしょう。
市場競争力強化
パートナー企業(協力会社)とビジネスを行う目的の1つに、「自社だけでは困難な目標の達成」があります。具体的には、パートナー企業(協力会社)の技術を生かした商品開発や、販路拡大による売り上げアップなどが挙げられます。
パートナー企業(協力会社)と製造・販売などに関するノウハウを共有したり、自社以外の観点を取り入れて業務改善を行ったりすることで新たな価値を生み出し、競争力の強化が可能です。
効率的な事業運営
パートナー教育は、スムーズな事業運営を長期的に行うためにも重要です。
自社とパートナー企業(協力会社)との間に、目標達成や日々の業務に対する意識の差が生じると、事業運営に支障を来す場合があります。
パートナー教育を通じて互いの信頼度を上げ、意識の擦り合わせを重ねることで、効率的な事業運営が可能になります。
パートナー教育を受ける企業側のメリット
教育を受けるパートナー企業(協力会社)側のメリットとして、以下の3つが挙げられます。
高度な専門知識・スキルの習得
自社とパートナー企業(協力会社)が共有するノウハウの中には、パートナー企業(協力会社)単独では得られないものもあります。より高度な専門知識やスキルを習得する機会を従業員に提供できることは、パートナー企業(協力会社)にとってのメリットです。
ブランド認知度向上
パートナー教育によって習得した知識やスキルを生かして商品・サービスの品質向上が実現すれば、顧客から高い評価を獲得できます。
「高品質な商品・サービスを提供する企業」として広く認知されることにつながり、投資家や従業員からの信頼を得やすくなるなど、さまざまなステークホルダーに良い影響をもたらすでしょう。
ブランド認知度の向上は、収益増加や優秀な人材確保の促進などにつながります。
ビジネスチャンス拡大・収益増加
パートナー教育で得たスキルを生かして事業の幅を広げることができます。これまでにないビジネスチャンスの獲得や収益増加も期待できるでしょう。
パートナー教育の方法
自社とパートナー企業(協力会社)にメリットをもたらす教育を実践するために、パートナー教育を成功させる4つの教育方法を見てみましょう。
集合研修
1つの会場に集まって行う集合研修では、座学やワークショップ、実技演習などを行います。定期的な集合研修は、自社がパートナー企業(協力会社)に伝えたい現場のルールやノウハウを直接発信でき、自社の理念や技術に興味を持ってもらうと同時に、知識の定着を促すことができます。
また、ワークショップや実技演習などにより、座学で得た知識を実践で生かせるか確認することも重要です。このような共通体験を通した学びは、自社・パートナー企業(協力会社)従業員の相互理解促進やチームビルディングにも役立ちます。
オンライン研修・eラーニング
オンライン研修やeラーニングには、集合研修にはないメリットがあります。インターネット環境とデバイスがあればどこでも受講可能で、時間や場所にとらわれないフレキシブルな研修が実現します。
ウェビナーやeラーニングは、全ての従業員に同じ情報・内容を提供できるため、講師によって教え方や分かりやすさが異なるという問題は起こりません。タブレットやスマートフォンで、繰り返し課題に取り組むことで、知識の定着も図れます。
また、集合研修にかかる宿泊費や交通費、会場の設営、資料の準備などが不要で、コストを削減できる点もメリットです。
OJT
OJT(On the Job Training)とは、上司や先輩従業員が指導役となり、実務を通じて知識やスキルを習得させる教育方法です。知識、経験豊富な上司や先輩従業員の下で行うOJTでは、個々の現状や業務に応じた実践的な知識やスキルを身に付けることができます。
また、OJTと併せてメンタリングを取り入れると対話を通して精神面からの支援が可能になり、パートナー企業(協力会社)従業員と自社従業員の信頼関係構築にも役立ちます。
教育資料の提供
どのような教育方法を取る場合も、パートナー教育で使用したマニュアルやガイドライン、よくある質問(FAQ)などの資料を提供しましょう。手元に資料があれば、パートナー企業(協力会社)の従業員がいつでも内容を確認できます。
内容を分かりやすくすることも重要です。例えば、漫画仕立てにする、イラストや図解を多用するなど工夫するとよいでしょう。
また、パートナー教育に用いる資料の内容に変更が生じた場合は適宜アップデートし、常に最新の情報を提供するようにしましょう。
効果的なパートナー教育の進め方
価値あるパートナー教育を実現するには、効果的な進め方も把握しておく必要があります。ここでは、パートナー教育の具体的な進め方をご紹介します。
ニーズ分析:現状把握と課題特定
まずは、パートナー企業(協力会社)にどのような教育が必要なのか、ニーズ分析をします。業務内容やスキルレベルといった現状把握から行い、パートナー企業(協力会社)が抱える課題を特定、解決のために必要な教育を明らかにします。
目標設定:具体的な目標と達成指標
ニーズ分析を基に、パートナー企業(協力会社)の課題解決につながる具体的な目標を設定しましょう。目的が明確でないと、パートナー教育を受ける意味や、パートナー教育によって目指す姿が不明瞭となり、従業員のモチベーションを下げる可能性があります。
また、目的の明確化は効果測定のためにも重要です。売上高や顧客満足度、商品知識習得レベルなど具体的な達成指標を設定し、教育プログラム終了後に客観的な評価を行います。
プログラム設計:適切なコンテンツと教育方法の選択
パートナー企業(協力会社)のニーズを満たし、目標達成に最適なプログラム設計を行います。
加えて、自社がパートナー企業(協力会社)に受けてほしい教育プログラムも準備しましょう。
教育方法は、研修(集合/オンライン)、eラーニング、OJTなどさまざまです。パートナー企業(協力会社)の規模や教育内容に合わせて適切な方法を検討しましょう。
複数の教育方法を組み合わせると、パートナー企業(協力会社)の従業員を飽きさせずに教育を進めることができ、目標達成に高い効果が期待できます。
運用体制構築:担当者アサイン、問い合わせ対応
教育プログラムが決まったら、指導やサポートを行う担当者を決める、問い合わせに関する体制を整えるなど、運用体制を構築します。
担当者は、円滑なパートナー教育の実施に向け、教育プログラムの進捗状況管理や、パートナー企業(協力会社)からの問い合わせ対応を行います。迅速な支援は、パートナー企業(協力会社)従業員の満足度向上を促し、パートナー教育を成功に導きます。
効果測定と改善:データ収集・分析、継続的な見直し
パートナー教育のプログラムが終了したら、効果測定と改善に向けた見直しを必ず行いましょう。
パートナー企業(協力会社)に向けたアンケートやインタビューなどで教育プログラムに対する意見や反応を積極的に収集し、それを基にプログラム内容や運用方法などの改善に取り組みます。効果測定と改善を継続的に行うことで、より効果的なパートナー教育が可能です。
パートナー教育に最適!安定稼働&スマホ学習もOKのLMS(学習管理システム) ⇒ ライトワークスのCAREERSHIPを詳しく見る
パートナー教育を成功させるためのポイント
効果的な教育プログラムに加え、自社・パートナー企業(協力会社)従業員のコミュニケーション促進やモチベーションアップにつながる施策などの実施も、双方に良い影響をもたらします。ここでは、パートナー教育を成功に導く5つのポイントをご紹介します。
経営層のコミットメント
自社とパートナー企業(協力会社)の経営層が、パートナー教育の重要性を理解し、積極的に支援することが重要です。
経営層が従業員に教育・研修の重要性を発信し、積極的に投資する姿勢を示せば、従業員もパートナー教育に前向きに取り組めます。
パートナー企業(協力会社)との円滑なコミュニケーション
パートナー教育をスムーズに進めるには、円滑なコミュニケーションを図り良好な関係を構築することも欠かせません。
例えば、定期的なミーティングは、自社の方針や求めるスキルを理解してもらうだけでなく、パートナー企業(協力会社)のニーズを把握するためにも有効です。また、パートナー企業(協力会社)からの疑問や意見に対して迅速に対応することも、コミュニケーションや信頼関係の強化に寄与します。
双方向のフィードバック
パートナー教育では、双方向のフィードバックを実施しましょう。
パートナー企業(協力会社)からパートナー教育への意見や要望を聞き取り、その内容を反映します。一方で、自社からの意見や要望もパートナー企業(協力会社)に適切に伝えると、教育プログラムのブラッシュアップと相互理解の深化が可能になります。
継続的な改善
パートナー教育は一度実施すれば終わりではなく、継続的に改善を行う必要があります。
教育プログラムを定期的に見直し、市場の変化やパートナー企業(協力会社)のニーズを反映すると、パートナー企業(協力会社)従業員の研修や勉強会に対する満足度が高まり、積極的に参加するようになるでしょう。状況に応じた最適な教育により、成果も得やすくなります。
効果的な学びが業務効率化、生産性向上につながり、パートナー教育の費用対効果をより高めることが期待できます。
インセンティブの活用
報奨金など、成果に基づくインセンティブを提供すると、パートナー企業(協力会社)のモチベーションやエンゲージメントを高められます。
例えば、韓国のテクノロジー企業、サムスン電子では「半導体協力会社インセンティブ」という制度を設け、生産性と安全目標を達成した協力会社に、年2回、数百億ウォン(数十億円/2025年2月4日現在)規模のインセンティブを提供しています。
2010年から2023年までに同社が支給したインセンティブの累計支給額は、6727億ウォン(約710億円/2025年2月4日現在)です。制度を導入した2010年と比較し、年間支給額は拡大しています[1]。
また、厚生労働省が公表する「化学工業における元方事業者・関係請負人の安全衛生管理マニュアル」[2]おいても、インセンティブ制度を設けることは安全確保への意欲の継続や意識向上に効果をもたらすとしています。
パートナー教育の企業事例
最後に、パートナー教育に関する企業事例をご紹介します。ぜひパートナー企業(協力会社)の教育プログラム設計の参考としてください。
鹿島建設株式会社
スーパーゼネコンの1つである鹿島建設株式会社は、次世代の担い手となる入職者をフォローする施策を積極的に実施しています。
同社と取引関係が深いパートナー企業(協力会社)で構成される「鹿島事業協同組合」と連携し「鹿島パートナーカレッジ」を設立、2021年4月に開講しました。
パートナー企業(協力会社)の人材育成を目的とし、担当の職種や工事に加え、現場や企業、建設業界全体を客観的に見渡せる広い視野の獲得とリーダーシップの強化を目指します。
鹿島パートナーカレッジで提供されているコースは、以下の2つです。
・テクニカルコース:同社の現場での業務に従事しながら、現場運営や関連職種に関する業務を学び、所定の単位数を3年以内に取得する
・マネジメントコース:パートナー企業(協力会社)と同社との間で出向契約を締結し、2年間で建設業界全般の知識・技能の他、企業経営に関する知識などを習得する
鹿島パートナーカレッジの設立により、パートナー企業(協力会社)の技能労働者や後継者のキャリアアップに関する支援の拡充が図られています。
住友商事株式会社
住友グループの大手総合商社である住友商事株式会社は、主要事業労働現場における災害ゼロへの取り組み強化に向け、2022年に災害・安全対策推進部内に「労働安全推進チーム」を発足しました。
国内外でビジネスを展開する同社は、幅広い分野で事業を拡大する中で労働災害の発生防止に向けて「グループ全役職員を対象とした労働安全教育研修」の必要性を認識しました。
そこで、ビジネスモデルや言語が異なっても正確に内容を理解でき、必要な知識が得られるよう、eラーニングを活用した安全衛生教育を実施しています。
オリジナルのeラーニング教材は、労働災害の危険性を我が事と捉えられるようにリアリティを追求するとともに、安全衛生に関する情報や知識を正確に分かりやすく伝えることを重視して制作されました。
eラーニング教材の導入によって労働災害への理解を深めた従業員からは、「自分たちが事故にあわないためにどんな対策があるのか」「これは労災に該当するか」という自発的な問い合わせが来るようになりました。
同社のeラーニングによる安全衛生教育は、全社的な安全や防災へのマインドセット定着に貢献しています。
この事例の詳細は、以下のリンクからご覧いただけます。
まとめ
パートナー教育とは、自社と共同でビジネスを行うパートナー企業(協力会社)の従業員に対して行う教育です。
パートナー企業(協力会社)から受ける影響は、事業規模やパートナー企業(協力会社)の役割が大きくなるにつれて高まります。そのためパートナー教育は自社の従業員への教育と同じくらい重要です。
パートナー教育の主な目的として、以下の5つがあります。
- 労働災害の防止
- 情報セキュリティ事故の防止
- 知識、スキル習得によるパフォーマンス向上
- パートナー企業の成長、事業拡大支援
- 長期的な関係構築とロイヤリティ向上
より良いパートナー教育の実践は、自社に以下のメリットをもたらします。
- 売り上げアップや生産性向上
- ブランド価値向上
- 市場競争力強化
- 効率的な事業運営
パートナー企業(協力会社)が教育を受けて得られるメリットは、以下の通りです。
- 高度な専門知識・スキルの習得
- ブランド認知度向上
- ビジネスチャンス拡大・収益増加
パートナー教育の主な方法として、以下の4つがあります。
- 集合研修
- オンライン研修・eラーニング
- OJT
- 教育資料の提供
パートナー教育は以下の手順で進めると、高い効果が期待できます。
- ニーズ分析:現状把握と課題特定
- 目標設定:具体的な目標と達成指標
- プログラム設計:適切なコンテンツと教育方法の選択
- 運用体制構築:担当者アサイン、問い合わせ対応
- 効果測定と改善:データ収集・分析、継続的な見直し
パートナー教育を成功させるために意識したいポイントは、以下の5つです。
- 経営層のコミットメント
- パートナー企業(協力会社)との円滑なコミュニケーション
- 双方向のフィードバック
- 継続的な改善
- インセンティブの活用
最後に、独自のパートナー教育を行う企業の事例をご紹介しました。
- 鹿島建設株式会社
- 住友商事株式会社
パートナー教育は、未来を見据えた人材育成施策の1つです。効果的なパートナー教育は、パートナー企業(協力会社)はもちろん、自社にも良い影響をもたらします。方法や実施手順などを改めて確認し、パートナー教育の充実を目指しましょう。
[1] サムスン電子「苦しい時も嬉しい時も協力会社に提供する共生インセンティブ!」,『SAMSUNG』,(閲覧日:2024年11月25日)
[2] 厚生労働省「化学工業における元方事業者・関係請負人の安全衛生管理マニュアル」,P104,2011年2月公表,(閲覧日:2024年11月25日)
参考)
鹿島建設株式会社「協力会社の人材育成を目的とした「鹿島パートナーカレッジ」を設立」,『鹿島』,https://www.kajima.co.jp/news/press/202010/27m1-j.htm(閲覧日:2024年11月25日)